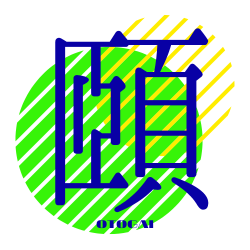ツイステッドワンダーランド/トレイ・クローバー×リドル・ローズハート
2022年1月22日ワンライ参加作品 お題:猫 ※Dの他作品の楽曲からの引用があります
既に始まっている演奏。色とりどりのライトが数秒ごとに切り替わっては、フロアを照らす。ステージにいるのは、事前に聞いていたロイヤルソードアカデミーのジャズ研究会ではなく、ガイコツのペイントをしたマリアッチたちだった。あまり広くはないクラブは、”友達の他校の友達”にまでチケットが配られただけあって、満員御礼とは言い難い。けれどその場にいた全員が、耳を傾けたり、踊ったりして思い思いに音を楽しんでいた。
「……演奏会、って雰囲気じゃあ、ないね」
「というよりは、ギグか?」
「お、二人とも、今着いたとこかにゃあ~」
「チェーニャ! キミ、嘘の時間を教えたのかい? もう始まっているじゃないか!」
「大体この時間に演るでって言っただけだがね~こういうのは、途中から来て途中で帰ったっていいもんだにゃあ~」
ドリンクを片手に持ったチェーニャが、すぐにトレイとリドルを見つけた。友達が演奏会をするから来ないかとくれたチケットは、その実複数の小さな音楽系の部活が割勘で麓の町のハコを借りて好きなようにする、という主旨だったらしい。確かに律儀に最初から最後までいる必要はないらしく、出入口では度々人がすれ違っている。
「ロイヤルソードのことをお坊ちゃん学校なんて言うやつもいるが、結構こういうところで遊んだりもするんだな」
「キミだけが自由なんだと思っていたよ、チェーニャ」
「ま、確かにマジメなカタブツもいるがねぇ。——その点あいつらは最高さね」
チェーニャはステージを振り返った。件のチェーニャの友人たちらしい。数人の猫の獣人属たちが、上機嫌に尻尾を揺らしながら、配置についた。
出だしは抑えめで、ベースとリズムとボーカルの歌声だけを響かせる。
『Everybody wants to be a cat——』
猫だけが、知っている。ものの道理を。イカしたスイングを。真に素晴らしいものを。自由を。
最初のサビが終わってから、他の楽器たちが加わって、最初の盛り上りが起こった。ドリンクを飲み干したチェーニャが、身振りでリドルとトレイをダンスに誘う。壁の花になろうとしたトレイの手を、リドルが少し強引に引く。
「俺はいいから、二人で踊ってこいよ」
「ボクだって、社交ダンス以外はわからないよ! ボクを一人にする気かい!」
リドルが、少し悪戯っぽく笑うので、トレイはぎこちなくビートに合わせてかかとを踏んだ。二人のどこか真面目さが残るぎこちない踊りを、嘲笑うものは誰もいない。
「リドルは猫になってみたいかにゃあ?」
頭の上を指すようなジェスチャーをして、チェーニャがリドルに問いかけた。
「どうだろう? この歌が言うように、猫だけが素敵なものを知っているとして——それは、少し悔しいから、なってみたいかもね」
リドルは、自分が何かを知らないことや想定していなかったことに厳しい。雨に降られてオクタヴィネル内を走り回った時だって、自分の備えが甘かったことを気にしていた。けれどその分、常に経験を生かそうとする。トレイは今日もリドルが折り畳み傘を鞄に忍ばせていることを知っていた。
「トレイは?」
「俺か? リドルが猫なら——俺は——」
暖炉の火かひなたになりたい。猫のリドルの肉球を、柔らかな毛皮を暖めるものになりたい。帰る場所に、安らげる場所になりたい。そう言うのは少し気障な気がして、トレイは「俺もなってみたいかな」とはぐらかした。猫と猫でも暖は取れる。
「やっぱり降ってきたな」
昼過ぎ開場のイベントは、学校の門限に間に合うようお開きとなった。厚い鉄扉をくぐって外に出ると、予報通りにポツポツと雨が降り始めている。リドルが鞄から出した傘を手慣れた様子でトレイが受け取って差す。
「今日は楽しかった。呼んでくれてありがとう、チェーニャ」
「それは何よりだにゃあ」
「次があればケイトも誘いたいな」
小さめの折り畳み傘の下で寄り添う背中を見送って、チェーニャはにまにまと目を細める。傘の柄で重ねられた手と手の意味を、勿論猫は知っている。以前よりずっと自由な心で寄り添う二人が嬉しくて、チェーニャは、もう一度踊り出したくなった。