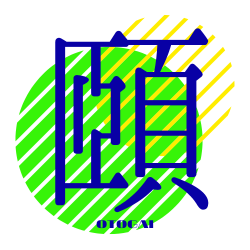トレリド子育て時空同人誌『Choose your own Wonderland』書き下ろしの『インタビュー・ウィズ・プラッシュ』(4p)『辺獄ホリデースペシャル』(13p)のサンプルです。
※『辺獄ホリデースペシャル』は死ネタです。
もしもトレリドが若くして亡くなって、ケイトとエースとデュースで子供たちを育てることになったら……?というifルート。
インタビュー・ウィズ・プラッシュ
小生はぬいぐるみである。ハートの女王の伝令の白ウサギを模したもので、それをマスコットとする運送会社とぬいぐるみメーカーのコラボ品である。ナイトレイブンカレッジの購買部で五十ほど積まれて売られていたところを、オンボロ寮の監督生に購入された。オンボロ寮のゲストルームで自我もなくぼんやりと放置されていた小生を特に愛顧してくれたのが、若かりし頃の父上殿である。その辺りはご承知おきのことかと思われるが、小生の物語はここから始まるのでご容赦いただきたい。父上殿が学園を卒業する際、餞別の品として小生は譲渡された。ベッドサイドに置かれた小生は、父上殿が勉学に励むのを見守り、実習に勤しむのを癒してきた。しかしその合間を縫っての若かりし日のパパ上殿とのデートこそが、父上殿にとっての活力となっていたことであろう。それも見届けてきた。パパ上殿がたまに小生を壁に向けるのを甘んじて受け入れていたとも。さて、二人が一緒に暮らし始めてから小生の居場所はリビングのソファの上になった。家に揃わない日は傍らで無聊を慰め、二人揃った日には二人の間に挟まれて緩衝材の役目を果たした。挟まれてみた映画で、一つ続編が気になるものがあったのだがあれはどうなったのか? ……いまだに製作が頓挫していると。それは残念なことだ。
やがて小生の職場はベビーベッドの中へと移った。一番上の姫君はそれはもう腕白で、お相手するのは大変だった。ごっこ遊びでは副官役や捕虜役を務め、どこへでも耳を引かれてお供したとも。そんな姫君が、小生に最後に下した命令が、中の若君のことだ。
『いいかい、赤ちゃんについてておやり! よーくめんどうをみてやるんだよ!』
そんな風に父上殿の口調の真似をして、小生をベビーベッドへぽい、と投げ込んだ。そして若君が小生の手をぎゅ、と握った時、彼が小生にとっての〝特別なこども〟だとすぐわかった。〝特別なこども〟というのはおもちゃたちにとっての信仰のようなもので、それに出会うことはこの上ない幸福なのだという。確かに、小生の若君との日々は、素晴らしいものだった。若君はいつでも小生を優しく抱き締めてくれた。たどたどしく絵本を読んでくれて、食べ物のないお茶会にお招きしてくれた。嬉しいときは一緒に笑って、悲しいときはその涙を吸った。
辺獄ホリデースペシャル
ローズハート=クローバー一家の三きょうだいは、一夜にして孤児になった。交通事故だった。子供三人となるとクローバー家側の親戚には生憎と余裕がなく、ローズハート家の祖母に引き取られることとなったが、それは子供にとってけしていい環境ではなかった。祖母はかつてリドル・ローズハートにした抑圧をやはり繰り返さずにはいられなかったし、十一歳の長子、シャーロット・ローズハート=クローバーはそれに抗わずにはいられなかった。優しい両親を知っていたからこそ、弟妹を守れるのは己だけだという自負が強くあった。残念ながらその庇護が、「けして大人に心を開くな」「お前たちのためなんだ」という新たな抑圧に変わるまでそう時間はかからなかったが。物心ついたばかりの末子はともかく、七歳の次子がそれに耐えられるはずもない。祖母と姉の板挟みの中で、彼、ロラン・ローズハート=クローバーは何度も助けを求めた。誰に? ——彼がこの世で最も大好きな大人、ケイト・ダイヤモンドに。手紙は切手代が足りなくて戻ってきて、公衆電話からかけた電話は繋がらなかった。エレメンタリースクールのパソコンルームから出したメールも、学内のイントラネットから出られず、どこへも届かない——はずだった。一人の非常勤講師がそれを見つけて、その文面の悲壮さに胸を打たれた。彼女はすぐさま児童の保護を専門とする団体〝ツイステッドワンダーランド児童救助救援協会〟に相談し、メールは無事、ケイトへと届けられた。
救助救援協会の仲立ちのもと、重苦しく長い話し合いが何度も重ねられ、最終的に子供たちは三人ともケイトが引き取ることに決まった。
小さな家での四人暮らしは、ほどなくエース・トラッポラやデュース・スペードが転がり込んできて賑やかな六人暮らしになった。時々アルチェーミ・アルチェーミエヴィチ・ピンカーも顔を出し、子供たちを驚かせては、凍えた心を少しずつ溶かしている。
そんな暮らしが始まって、まだ半年も経っていない。
まだぎこちなさや悲しみの陰が降りる中、急拵えの一家は初めてのウィンターホリデーを迎える。
末っ子のエディス・ローズハート=クローバーが朝食のシリアルを食べているのを見ながら、ケイトはコーヒーを入れていた。昨日プリスクールでホリデーツリーを飾ったと話し始めたので、最大限さりげないタイミングはここしかないと、ツイステッドワンダーランド中の大人たちが頭を悩ませている質問を繰り出す。
「イーディはサンディ・クローズに何をお願いするの?」
それは子供なら誰もが尋ねられるお決まりの質問。だが彼女にとっては初めてのものだった。
「ぱぱとおとーさまにあいたい!」
「えっ」
「さみ〜! おはよーございま〜す」
「イーディ、ダイヤモンド先輩、おはようございます……」
ケイトが言葉を失っていると、珍しく休日が重なったエースとデュースが眠気をこらえながら起きてくる。子供と暮らすようになってから、二人は休日でも規則正しい時間に起きるようになった。
「あっ、エーくんデューくん、おはよ〜! あのねー、サンディさんにねー、ぱぱとおとーさまに会わせてもらうんだー」
「……えっ?」「えーっとぉ……」
三歳の純真な願いに大人たちは硬直する。いち早く動いたのはデュースだった。
「……あのな、気持ちはわかるけど、それは——」
「わ゙ーっ! 待った待った!」
末っ子に目線を合わせ、正直に真実を告げようとしたデュースの口を、咄嗟に塞ぐエース。
「子どもの夢をぶち壊すのはよくないっしょ!」
「適当なことを言う方が良くないだろ! 無理なものは無理って言わないと……」
エディスは小声で言い争うエーデュースをきょとんと見つめていたが、やがて牛乳でふやけたシリアルをスプーンで掬うのに集中し始めた。さて大変なことになったぞ、と思いながらケイトは、「ピンクのシリアルもちゃんと食べな〜」と言うのだった。
それはさておき、一方ここは地獄。よほどの善人か赤ん坊でなければ、死後大体の人間が訪れるゴーストの世界である。
地獄らしい荒れ地に、ブラウン管テレビが一つ置かれていた。その前には死体の山。いや、既に死んでいるのでこれ以上死ぬことはない。一時的に動けなくなるだけだ。それは逆に言えば、腕がもげようと首が落ちようと、苦しみから逃れられないということだった。
二人の死者が、その山をかき分けて血肉に汚れたリモコンを拾い上げた。電源ボタンを押すと、テレビに光が灯る。ノイズと砂嵐が走って、死者のうち片方——トレイ・クローバーがテレビの上面を軽く叩く。やっと映像が安定して、シットコムのような映像が浮かび上がった。ケイトとエースとデュースと、エディス。
『あのねー、サンディさんにねー、ぱぱとおとーさまに会わせてもらうんだー』
オーゥ、と大げさな嘆息のエフェクトが被せられる。もう一人の死者——リドル・ローズハートは膝をついた。その隣にトレイも座り、肩を抱く。
「……帰らないと。ウィンターホリデーまでに」
「……ああ、そうだな」
「ちょちょちょ、待って!?」 いつの間にかテレビの隣に地獄の住人が立っていた。悪魔、あるいは死神か。どちらにせよ、今日のそれは、なぜかトレイとリドルの記憶の中にあるイデア・シュラウドの容姿と声をしていた。姿を変えられるせいで、この死者たちのチャンネル権争いを見に来ているのがいつも同じ悪魔かどうかもわからないが。