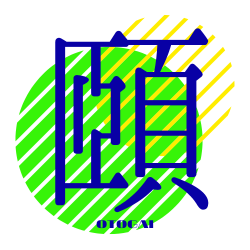トレリド子育て時空で、『インサイド・ヘッド』『インサイド・ヘッド2』のパロディです。
二人はただただ無言で唇を噛み締めていた。病室のベッドには長女が寝かされている。外傷はなく、普段の寝顔とそう変わらないが、現在進行形で精神の一部を盗まれている。次に目覚めたとき、元通りの彼女かどうかもわからない。あるいは、このまま目覚めることはないかもしれない。彼女が遭ったのは、そういった被害だった。ミドルスクールの後、ふらりといつものように外へ出て、帰ってくるなり『気分が悪いから少し休む』と部屋に行き、夕食に降りてこなかった。不審に思って見に行くと、昏睡状態になっていて、何者かに魔法をかけられた痕跡があって——。
「失礼します」
病室に入ってきた二人連れの出で立ちに、トレイはぎょっとして目を見開き、リドルは不快感と警戒心を露にした。
「あのう、シャーロット・ローズハート=クローバーさんのご両親ですね? わたくし担当警察医の——」
二人連れのうちの片方、くたびれたコートの中にピエロのような衣服を着、顔面を化粧で真っ白に塗っている中年男性が差し出した名刺を叩き落とさん勢いで、リドルは立ち上がる。
「この非常事態に、よくもそんなふざけた格好で来られますね!」
「リドル、落ち着け」
「落ち着いていられるか! こんなのをあの子の頭に“入らせる”だなんて——」
「あ、私は命綱を握っているような立場でしてね。実際に潜行するのはこちらの魔法執行官になります」
「……ス」
後から入ってきた若い馬の獣人に対しても、リドルはウギギギギ、と歯を食い縛る。どう見積もっても地毛ではない傷んだ七色の髪に、一本角のついたカチューシャ。おまけに態度も無礼だ。
「我々も意味もなくこんな格好をしているわけじゃあないんですよ。なるべく夢だと思ってもらえるように、現実離れした見た目の方がいいんです。それにほら、女の子は特に好きでしょ、ユニコーン」
「あの子はユニコーンなんか好きじゃないッ!! ますます信用ならないッ!!」
「すみません、夫は気が動転していて……」
「いえいえ、無理もないことです」
記憶泥棒。それはツイステッドワンダーランドでは稀にある犯罪だった。精神に干渉する魔法を使用して、他者の記憶を盗みとる、おぞましい犯罪だ。企業スパイ目的のこともあれば、子供や女性を狙った純粋な加害目的のこともある。今回のケースは、おそらく後者だった。
「もういい、ボクが潜行して犯人を捕まえる!」
「いやあ、ローズハートさんは魔法医術士とお聞きしていますが、治療はまだしも捜査は訓練を積んだ魔法執行官でないと……」
「ウギ……」
「それにねえ、親御さんですとか、あまり普段から関わりの深い人間が記憶に触れるのは魔法倫理学上好ましくないんですよぉ……」
「警察医さんの言うとおりだ、リドル。親である俺たちは冷静に待っていないと」
「……そうだね、トレイ。すみません、取り乱してしまって……信じていいんですね?」
リドルが必死に息を整えながら警察医と魔法執行官を見据えた。その時だった。
「ウッ……!」
もともとフラフラと立っていた魔法執行官が、バターン! と受け身なく倒れた。気まずい沈黙が流れる。
「……ああ、だから三日前のカップケーキはやめておけって言ったのに……」
「……はあ?」
「やっぱりダメじゃないか!!!!」
単に不愛想なだけでなく、体調不良でもあったらしい。ストレッチャーで運び出されていく魔法執行官を、ピエロの衣装の警察医は「ここが病院でよかったね~」と見送った。
「いやうちの若いのが自己管理能力不足で本当~~~にすみません。お二人に潜行の方法をお教えするので一発で覚えてくれませんか?」
警察医はしゃあしゃあと言ってのけた。
「残念ながら代わりの魔法執行官を呼ぶ猶予はありません。ご両親揃ってNRC出の魔法士で、本当にラッキーでした」
リドルは怒りに目を白黒させながらも、警察医が一転して真剣な顔になったのを見てウギ……と唸りを飲み込んだ。トレイは深くため息をつく。
「まったく……!」
「俺たちでやれるなら、やるしかないか……」
***
「あくまで、記憶に関する魔法を扱う者たちの間で共有しているイメージにすぎませんから、実際に脳の中がそうなっているわけではありません。人間の精神という広大な世界で迷ってしまわないために当てはめる、地図のようなものです」
警察医はそう前置きして、メモ帳にささっと図を描いた。中心に司令部。司令部から繋がる性格の島。その下の周囲に広がる記憶の迷路。更に下には無意識の谷。
「このイメージはとてもメジャーなもので、おそらくホシもこれに則る可能性が高いでしょう。いいですか、司令部を目指してください。ホシがお嬢さんのどんな記憶を狙っているのかは全くわかりません。ですが記憶というのは膨大なもので、その中から闇雲に望むものを探していては時間がかかりすぎる。必ず、司令部の”思い出す”機能を使うはずです。そこへ、ホシより先にたどり着いて防衛するんです。そしてのこのことやってきたところにローズハートさんのユニーク魔法を使えば、ホシを、記憶泥棒を追い出せるはずです」
「泥棒に先を越された場合は?」
「目的を果たしたら記憶泥棒は必ず逃走経路を作るはず。私が命綱を握っているあなた方と違って、自力で離れたところへ浮上するのは時間もかかるし困難になります。そこを叩くことも可能でしょう。ですが、記憶の配置を他人がいじってしまえば、どんな影響が出るのかわからない……。とにかくいち早く辿り着くのに越したことはありません」
「泥棒に遭遇して……追い出すだけで捕まえることはできないのですか?」
「そうですね、初めてですからそこまでは難しいでしょう。ですがもし余裕があれば
……私の付け鼻に似た色のカラーボールをイマジネーションで作って投げつけてください。それをアンカーに相手の情報を引っ張ることができるかもしれません。」
「もし記憶泥棒が我々と同じ脳内のイメージを採用していない場合は?」
「そんなにユニークなイマジネーションがあれば、女子中学生なんか襲わずスパイやセラピストとして大活躍のウハウハ生活してますよぉ〜……おっと、すみません」
二人にじとりと睨まれた警察医は、慌てて聴診器に似た魔法道具を取り出すと耳にかけた。チェストピースのような吸盤を長女の額に押し当てる。そしてトレイとリドルに左右の手を伸ばした。
「とにかく、司令部です。中心の高いところを目指してください。脳は広いですから、急いで——」
トレイとリドルがその手を取ると、意識がどんどん遠ざかって何かに沈み込んでいく。
***
はっと目が覚めると、光に包まれていた。それなのにどこか薄暗かった。実体としての感覚があるようなないような、不思議な感覚で足元を確かめる。
「本当に……あの子の脳に入った……のか?」
「トレイ! 無事に二人とも潜行できたようだね。あの警察医、信用ならなかったけれど……」
「リドル! ……リドル?」
ああ、そうだな、と相槌を打とうとしたのに、トレイは首を傾げた。
「お前……なんかちょっとでかくないか?」
「……きっと、あの子から見たイメージなんだろう。キミだって……大きいよ」
脳内の二人はどこかアニメーションのキャラクターのようなデフォルメがされていて、リドルはすらりと背が高かったし、それよりも大きなトレイは肩幅ががっしりとしすぎていた。リドルの背丈をとっくに追い抜いているくせに、あの子にとって自分たちは”大きな”存在なのかと思うとなんだかくすぐったい気がした。
「ところで、ここが……”記憶の迷路”か?」
二人立つ通路の壁には、様々な色の球が収められている。ランダムに一つ覗き込むと、エースが指からコインを出して、視点の人物——あの子が、その手に飛びついて広げている記憶が見えた。警察用のマジカルホイールに載せてもらい、デュースの背にしがみつく記憶。マニキュアで爪を黒く塗っていたら、まだ乾かないうちに服に引っ掛けてしまう記憶。ギターを弾くケイトのメトロノームアプリを勝手に早めてしまういたずらの記憶。ソファでテレビを見ていると弟が隣に座って本を読み始める記憶。妹を抱き上げて赤ちゃん用の椅子に座らせてやる記憶。トレイのメガネを勝手にかけてみて、くらりとした記憶。リドルの書斎で積まれた本を崩してしまい、適当に元に戻す記憶。
迷路の壁は果てしない。時系列も色も様々な記憶が、無数に並んでいた。耳を傾ければ、声や音が次々に聞こえてくる。
「見入ってる場合じゃないな、早くここを抜けないと」
「わかっているよ。あの子にだってプライバシーはあるしね……うん?」
そう言いながらも、一つの記憶がリドルの目に留まった。赤く、鮮明で、とても新しいものに見える。
『おっさん、その子困ってるじゃん』
記憶の中で、あの子は路地裏に追い詰められた女の子を見つけていた。子供用のリミッター付きマジカルペンを構えて、男の背中に突きつける。
『丸焦げにされたくなかったらその子から離れな』
このマジカルペンでは、爪の先ほどの火がせいぜいで、人を丸焦げにするほどの火力は出ない。けれどあの子は少しも怯まずハッタリをきかせていた。
男が溝のような暗い目で振り向く。両手を上げてゆっくりと振り向く。ブツブツと口の中で何かを呟く。
『あ? 何——ッ!?』
あの子を突き飛ばして、男は横をすり抜けた。慌てて後を追うが、路地を出るともう人混みに紛れていなくなっていた。イライラしながらダン! と地面を一度踏みつけると、深く息をついて袋小路の女の子に向き直る。あの子と同年代、ミドルスクール程度だろうか。膝丈のスカートを握りしめてガタガタと震えている。
『大丈夫? 病院とか行く? ていうか追っ払っちゃったけど、知り合いとかじゃなかったよね?』
女の子はわっと泣き出すと、あの子に抱きついた。その背中をさするところで、その記憶は終わっていた。
「これ、昨日の服だな……。こういう経緯だったのか」
「……つまり、今の男が、女の子を襲って、うちの子にターゲットを変えて、うちの子を昏睡させて、記憶を盗もうとしている記憶泥棒かい……?」
リドルの顔がたちまち真っ赤に染まっていく。冷静さを失っていく。今にも果てしない迷路を突っ走って行きそうなその手を、トレイはぎゅっと握った。犯人を追い出すだけならリドルだけで足りるだろうが、この通りリドルは激昂しやすい。まして大事な子供を傷つけられて怒り狂っている。その手綱を握るために、トレイはリドルを一人では行かせなかったし、短い時間で警察医もそうすべきだとわかっていた。
「本当に許せないよな。早く”司令部”に行かないと……。何か移動手段があればいいんだが」
「…………あの子の頭の中なら、絶対に箒があるはずだよ。”性格の島”だったかな? そこを目指そう。ひとまず迷路の上に登って辺りを見てみようか」
荒い息を鎮めて、やっとリドルは落ち着きを取り戻した。トレイが風の魔法で上昇気流を作り、リドルがジャケットをパラセール代わりに飛び上がる。その後木の魔法でトレイを引っ張り上げた。迷路の上に立つと、その気が狂いそうなほどの広大さがよく見えた。迷路の上空には浮島がいくつもあり、そこから高い塔へと道が伸びている。あれが”司令部”だと、ひと目でわかった。
二人は迷路の上を走って、一番近い島へとたどり着く。幸運にもそこには、あの子の好きなものがひしめき合っていた。マジフト用の箒にディスク、サッカーボールに野球ボール、バット、クロッケーのフラミンゴやハリネズミ、あの子が好きなスポーツでできた島かと思われたが、満点の答案やトロフィーの塔もあって、それだけではないと察せられた。
「”優秀の島”……ということかな。あの子は自分が優秀であることを証明するのが好きなんだと思う」
リドルは穂先が乱れた箒を手に取る。中学のマジフト部の試合でプレイ中に地面を大きく擦った時のものだ。あわや地面に落ちるかと思われたが、あの子は超低空飛行で相手チームの包囲をかいくぐって、勝利に繋がるゴールを決めた。
「お前の言った通り、ここはあの子の物でいっぱいだな……」
トレイは少しフレームの小さな自転車を選ぶ。箒はまだ早いと言われた時に、無理矢理飛ばそうとしたものだ。大きなトレイの身体をみっしりと納めて、自転車はよたよたと飛び上がる。今はもう末の子に譲られた、その塗装が褪せていないのがなんだか懐かしくてこれを選んでしまった。「ふざけている場合かい!」リドルの咤とは裏腹に自転車は予想外にスピードが出て、箒を束の間追い越した。これが危ないから、七歳の一時期自転車を没収していたのだ。
その時、地面が大きく揺れた。二人は島の端を振り返る。島の端がぽろぽろと崩れ落ちていた。
「……記憶泥棒のせいか? それとも、勝手に取ったらまずかったか?」
「……どちらにしても、急ごう」
二人は猛スピードで脳の中心を目指して飛ぶ。
***
司令部の窓は割れていて、二人はそこから侵入することができた。胸騒ぎに顔を見合わせて突入すると——先程の記憶で見た通りの男がいた。蓋に空気穴の空いたジャム瓶に押し込まれて身動きが取れなくなっている。それを挟んで、色とりどりの光でできた身体を持つ生き物たちが議論している。
「こんなのに入り込まれるなんて! あの子は今普通の状態じゃない!」
「やっぱり”秘密”があの子を弱くしているんじゃ?」
「それとこれとは関係ないだろう!」
「どうしてそんなことわかるのぉ?」
紫の光でできた生き物がトレイとリドルに気がついてうわあ! と声を上げる。
「おしまいだ、両親に頭の中に入られるなんて……」
「本当に最悪、プライバシーとかないわけ?」
緑のものも嫌悪に顔をしかめる。
「悪いと思っているよ! そこの瓶に入っている男を捕まえに来たのだけれど……」
黄色のものが嬉しそうに瓶に抱きつく。
「それならもうみんなでやっつけて捕まえちゃったわ!」
「俺達の出る幕はなかったか……あの子は我が強いからな」
「きっと記憶泥棒は、本来もっと大人しそうな子を狙うつもりだったのだろうね」
脳内では脳の持ち主が本来一番強い、と監察医も言っていた。だから泥棒は意識を落としたのだろうが、それでもあの子の脳内の者たちは自分で犯人を打倒したらしい。
赤、青、黄、緑、紫、ピンク、オレンジ、水色、群青の光たちは、あの子の感情だと名乗った。
「ただでさえ感情が増えたばっかりで大混乱だっていうのに……」
「上手く引き継ぎしてくれなくてダルいんだよね、原始的な感情の方々がさ」
「原・始・的ィ〜!?」
嫌悪と倦怠が小競り合いを始める。記憶泥棒を撃退するのには一丸となったものの、仲良しチームというわけではないらしい。これまで喜び、悲しみ、嫌悪、恐怖、そして怒りしかなかったところに、羞恥、心配、羨望、倦怠が来て思春期が始まったところのようだった。
「まあ確かに感情がシンプルな子ではあったよな……にしてもちょっと思春期に入るのが遅くないか?」
「発達は人それぞれだからね……」
二人の言葉に、心配が一つの記憶を差し出す。それは赤とピンクと青に彩られて光っていた。
「あの子にもやっと大人になるための感情が必要な時が来たんだよ。お父様は知っているでしょ」
その記憶の中で、あの子は夕暮れ時のキッチンの入口に立っている。リドルが夕食の支度をしている。つい昨日のことだ。あの子の三者面談のために、リドルは午後休を取った。
『キミが魔法医術士になりたかったなんて、知らなかったよ』
『あれ? 言ったことなかったっけ?』
『ないとも。キミはいつも、キミの中だけで自明のことを言うよね。もし本当になるつもりなら、そういうところは直すべきだ』
『……本当になるつもりならって、何?』
『いや、キミの覚悟を疑ったわけではないんだ』
『なってほしくないんでしょ』
リドルが包丁を置き、あの子に向き直る。
『キミは患者をクリアすべき課題やステップアップの足がかりとして捉えてしまいそうで、不安だよ。患者は生きている人なんだ。親の目から見て、キミが生きた他人のケアをする仕事に向いているように見えない』
『……』
数秒の沈黙の間、リドルは言いすぎたか思案するように目を伏せていた。
『どうしてもなりたいなら勿論応援するけれど……』
一度手を洗って、努めて優しい声をかけながらあの子の肩に手を置く。けれど表情はまだ険しいままだ。この親は、優しい嘘をついたり、取り繕ったりするのが本当に苦手なのだ。
『それは、本当にキミのやりたいことなの?』
それを振り払って、あの子は足早に家を出ていった。そこでその記憶は終わっていた。
「……このことについては、キミも交えて話し合うべきだと思っていたんだ。なのにこんなことになってしまって……」
「そうか……。気持ちはわかるが、もっといい伝え方はあったかもしれないな……。俺が帰るまで話を待っててほしかった」
「……ごめん」
リドルは心底悔いながら謝る。そして今度こそしっかりと話し合うためにも、記憶泥棒を片付けなければ、と顔を上げた。
「これ以上あの子の頭に長居するわけにはいかない。その男を引き渡しておくれ」
しかし心配は瓶との間に立ちふさがる。
「今の記憶を見てもらったのは、私たちの頼みを聞いてほしいからなの」
「ちょっと! 勝手なことしないで!」
喜びや嫌悪、悲しみと恐怖が叫ぶが、羞恥や羨望も瓶の前に立ちふさがった。”頼み”については、感情たちの間で意見が割れているらしい。足を踏み鳴らしながら心配の側についた怒りを、嫌悪が詰る。倦怠はただ横たわっているだけだったが。
「この会話がきっかけで、あの子の優秀さは揺らいでいる。でもあの島を支えている特別な記憶は、秘密の保管庫にしまい込まれているの。それを取ってきてほしい」
「断る。ただでさえあの子のプライバシーを侵害しているのに、まして秘密だなんて……」
「というか、お前たちはあの子の感情なんだろ? 知らない記憶があるのか?」
「私たちはあの子のほんの一部なの。全てを知っているわけじゃない」
頑として譲らない秘密を求める記憶たちに、トレイはため息をついた。
「しょうがない。ここじゃお前たちのほうが強いんだろ? 取りに行くしかなさそうだな」
「……それで、秘密の保管庫というのはどこにあるんだい」
リドルも不承不承頷いた。絶対に許されることではないとわかりながら、そうするしかない。それはリドルの性分にとって耐え難い苦痛だったが、それを押してでも、娘を助けなければいけなかった。
***
「優秀さの問題では……ないのだけれど」
「だからこそ、このままでいいのか心配になったんだろうな」
暗い秘密の保管庫の中を歩きながら、二人はあの子の進路について話し合っていた。なるべく他のものは見ないように最奥を目指す。
優秀でありさえすれば、他者を圧倒し続けていれば、何にでもなれるし何もかも手に入れられる。きっとそう思っていたのかもしれない。けれどそうではないことをリドルはよく知っていた。
「あの子の夢を、トレイは知っていたの?」
「……いや、俺も知らなかったよ。あの子はもっとこう、俺達の常識の外側のものを目指してると思ってた。単なる能力の話なら、実際あの子は何にだってなれるし、俺達の言う事なんか聞かないだろ……って」
「……あの子が本当になりたいと思っているのならね」
結局は、心の問題だ。あの子自身の。そしてあの子が他者に向ける。それが伴わない状態では、何になったとしても、いつか誰かがつらい思いをすることになる。あの子が誰かを傷つけるかもしれないし、あの子自身が傷つくことになるかもしれない。いつものあの子なら、「かもしれないで勝手なこと言わないで」と言うだろう。けれど彼女には、リドルの心配を跳ね除けるだけの、魔法医術士への憧れはなかったのだろうか。
奥底の壁に、記憶の球体が転がっていた。すっかり色褪せていて、今にも消えて無くなりそうに見えた。相当古いものなのだろう。リドルはそれを、小さな頃のあの子を抱き上げるように優しく拾い上げた。
「ちゃんと持ってきてくれた?」
司令部に戻り、心配にそれを引き渡す。心配はそれを見ると、更に怒りへと手渡した。
「ああ……そうだ、これだ。なんで忘れていたんだ……」
怒りの手の中で、記憶は赤く光り輝いていく。
それは、子供部屋の記憶だった。ブロックで一人遊びをしていたあの子は、足音を聞き取ると、ふざけてベビーベッドの下へと隠れる。
『あら? あの子……どこへ行ってしまったのかしら』
リドルの母が、入ってくる。一度だけ、真ん中の子が赤ん坊だった頃、やむを得ずあの人にベビーシッターを頼んだことがあった。あの子にとっての祖母は、赤ん坊をベビーベッドに寝かせながらこう言った。
『きっとあちらの側の血ね』
握り込んだブロックを床に置いて、あの子は耳をそばだてている。
『髪の色からしてあちらの血が濃いようだし、無理もないわ。魔法の方も期待できないでしょうね』
この頃のあの子は四歳ほどだろうか。意味は理解していたのだろうか。していたのだろう。あの子は、ベビーベッドの下から飛び出して祖母を驚かせることをしなかった。
『やっぱり期待できるのはこの子の方かしら……』
祖母が一度部屋から出ていく。あの子はベビーベッドの下から這い出すと、弟の寝顔をじっと見つめた。赤い髪をそっと撫でる。
『……ぜったいに、まもるからね……』
起こさないように小さな声で囁く。自分が優秀であり続けて注目を集めれば、きっと弟に害は及ばない。最後に青い悲しみの光を帯びて、その記憶は終わっていた。
「……これは……」
「なん、てことを言うんだ、あの人は!!」
唖然としたトレイより先に、リドルが激昂する。その横顔に、トレイはもう一度驚いた。子供ができて、いつの間にかリドルは母親に怒れるようになっていた。不謹慎にも、今はリドルの怒りへの瞬発力に惚れ直してしまっていた。
「こんな言葉、あの子は聞くべきじゃなかった……!」
リドルの怒りに、喜びも同調する。
「こんな記憶、酷い……! 記憶の彼方にふっとばしてしまわないと!」
秘密を開示する側に立っていた心配も頷く。
「確かめてみてわかった。四歳の頃の記憶にいつまでも縛られてるのはあの子にとってよくない。優秀の島は、崩れるべくして崩れてるんだよ」
トレイはリドルが怒ってくれた分、ずっと静かに考え込んでいた。そして重々しく口を開く。
「……本当にそうなのか? リドル、俺達はあの子の記憶の配置をいじるべきじゃないだろ」
「……っトレイ……! でもあの子の一部だってこう言うってことは、あの子だって忘れたがってるに決まってる!」
怒りは「いいや!」と記憶を奪われまいと抱きしめる。
「この記憶は……特別な思い出なんだ! この怒りがあの子の原点なんだ……! やっと思い出せたんだ……!」
「……あの子の一部であって、全部じゃない。俺は、元のところに戻すべきだと思う」
「でも……!」
トレイはリドルの両の手を握り、微笑んだ。もうあの子の記憶に触れるべきではない。親であっても。
「酷い記憶でも、これが今のあの子を作ってる。……俺も、わかるよ」
「……」
感情たちにも向き直る。
「お前たちが……あの子がこれをどうするかは任せるよ。でも、俺達は何も見なかった。これは秘密なんだ。それがいいよな?」
「……ああ」
怒りが記憶泥棒の瓶を差し出してくる。リドルは、マジカルペンを向けた。反対側の手はトレイと繋いだまま。
「『首をはねよ』——」
ピエロのつけ鼻と同じ赤に空間が染まる。トレイとリドルは、急激に浮上するような感覚に見舞われた。
労いの言葉もほどほどに、警察医は引き上げていった。記憶泥棒の身元を特定するために、早急に解析しなければならないという。二人は病院のベッド脇で、娘が目覚めるのを待っていた。
「再会したばかりの頃、キミの頭の中に入れたらって思っていたことはあるけど……実際入ってみると、人の脳というのは難しいものだね」
リドルはトレイの中の悲しみを、怒りを、恐怖を、嫌悪を思った。あの頃は、トレイの中のリドルはいつでもそれらの感情と共にあるのではないかと怯えていた。
「……ボクとの記憶がどんな色をしているか、知りたかった。辛いことをなかったことにできるのならそうしたかった」
もっと違う出会い方をしていればと何度も思った。勿論、今となってはあれしかなかったのだと受け入れているけれど。トレイは喜びの色をした瞳でじっとリドルを見つめて、微笑む。
「言っておくけどな、辛い記憶だけじゃない。嬉しい記憶が俺を作ってるんだ。俺にとってはどっちも大事なんだよ」
「……ボクも。それは、ボクもそうだよ」
微笑み返したリドルの喜びは、頭の中など見なくてももうわかっていた。
その時、娘が身動ぎをして、二人は椅子を蹴るような勢いで立ち上がる。
「ここ……どこ? え、ちょっと、何?」
ゆっくりと身を起こした娘を、二人は抱きしめた。頭の外で話し合わなければならないことがたくさんある。祖母の暴言と、この子が密かにユニコーンを好きなことは、知らないふりをしなければならないが。