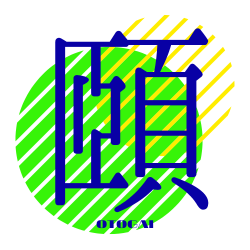ツイステッドワンダーランド/トレイクローバー×リドル・ローズハート
『トレリド持ち寄りパーティー』という、美味しいお題を持ち寄ってシャッフルする企画に参加させていただいた作品です。 受け取ったお題:食べ合わせ ちなみに私が持ち込んだお題は、「ピーナッツバター」です。
『食べ合わせ』という概念を初めて得たのはいつだったろう。子供向けのレシピ本のコラムだったような気がする。短くてさらりとした文章だったが、それは子供時代の俺に食材の組み合わせには無数の可能性が広がっていると無邪気に信じさせるのには十分だった。何気ない組み合わせで、単なる足し算以上の効果が生まれるかもしれない。「美味しい」以上の価値が。しかしまた別の本で、「組み合わせてはいけない」という考え方もあることを知り、理不尽さを感じたりもした。心理的なタブーに共感するには俺は少し鈍感過ぎた。医学的なタブー、食べ合わせによって生じた事故についてやや大げさに記述されているのを読んで首を傾げていると、横でチェーニャがうちの妹に『スイカを食べた後たくさんジュースを飲んだらへそから芽が出た』という話を聞かせて驚かせていて、それは本当に嘘だろう、と苦笑しながらも、俺はその嘘に乗ったのだった。
昼食の冷製スープを、あらかじめ冷蔵庫で冷やしておいた陶器のカップに注ぐ。トマトと、オリーブオイルの香り。これは、食べ合わせが「良い」方の組み合わせだ。揚げたてのフィッシュフライと、チーズを乗せてカリカリになるまで焼いたベーグルと一緒に、銀の盆でリドルの部屋へと運ぶ。
「リドル、お疲れ様。昼食を作ったから、一度休憩にしないか?」
「ああ、トレイ。ありがとう。キミはもう食べたのかい?」
「とっくにな」
「そう……ああ、もう14時なのか」
リドルは書類仕事に追われている。月末はその月の何でもない日のパーティーの精算や足りなくなった備品の発注、来月の計画や当番の割り振りで忙しいのだ。今は来月の各部活やクラスのスケジュール表を机の前面に張り出して、ああでもないこうでもないと付箋を動かしている。正直、どうしても個々人の用事で変更になることはあるし、ある程度の事情はあえて無視してざっくりと決めてしまってから寮生たちで交渉させればいいだろうと思うのだが、リドルは真面目なのだ。すっかり昼食が遅くなってしまっているリドルを案じて、俺は自発的にデリバリーをしようと思い立った。
応接机に食器を並べる。見られていては食べにくいだろうかと部屋を出ようとすると、「待って」と引き留められた。
「どうした? 何か話でもあるのか?」
「ええと、いや、何も無いよ。でも……ここにいてほしいんだ」
不器用な甘え方に思わず頬が緩む。やはり弟のように大切だ、と思う。実際の弟にはわざわざ食器を冷やしたりしないし部屋で食事を運んでやったりもしない。けれど俺がそうだと思うことにすれば、”そう”なのだ。
「このスープ、すごく美味しいね。今日は少し暑いから嬉しいよ」
「そいつはよかった」
冷製スープは冷たいまま、フライは揚げたてのまま笑顔で食べてもらえるのは嬉しいことだ。かつての鬼気迫るリドルなら、「そこへ置いておいて」とこちらを振り向くこともなかった。あの頃は後になって食器を取りに行く時の「美味しかった」だけで十分嬉しかったのに、俺はすっかり欲張りになったらしい。ベーグルをもちもちと噛む頬も、唇の端についたフィッシュフライのタルタルソースを舐める舌も、今は全て隣に座る俺のものだ。
「美味しかったよ。ありがとう」
スープを飲み干して、リドルは微笑んだ。
「冷たい飲み物と揚げ物は食べ合わせが悪いとお母様が言っていたけれど、後味をさわやかにしてくれてとてもいいね」
「えっ? 言ってくれたら温めたのに」
「いや、キミの気遣いと判断は完璧だよ。やはり料理に関してはキミの方が”正しい”」
少し狼狽しつつ、奇しくも食べ合わせのことを考えていたので俺はなんだかおかしくなってしまう。
「リドルも食べ合わせとかは気にするんだな」
「ボクが、というよりお母様がね。たくさんの組み合わせを教えてくれたよ。大半は医学的根拠があってのものだけれど、こうして食べてみると正直疑わしいというか、考えの古いものもあっただろうね」
あのリドルが、母親に対してこんな風に距離をとって考えることができるなんて。リドル自身の数々の体験がもたらした変化なのだと思うと、その一端に携われたことが嬉かった。
「適切な程度を守ればきっと何も問題はないんだろう? また、”適量”だね。悪くなるどころか、キミの料理のおかげでボクはまた頑張れるよ。ありがとう、トレイ」
面食らうほど真っすぐな心に触れる。冷たいスープのように優しくて凪いでいて、熱い揚げ油のように激しい瞳、空気、時間。再会してから今日まで得た全てが、冷たい水と熱い油が混じり合うような劇的な効果をリドルに、そして俺に与えていたのだと、その時はたと理解した。
「……トレイ?」
ああ、まるで胸やけをしているみたいだ。喉に感情が詰まって、何も言葉が出てこない。この感情の正体を自覚するのは、あまりにも苦しい。