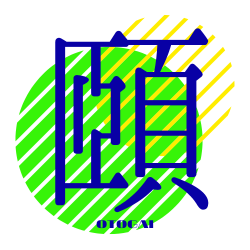ツイステッドワンダーランド/トレイ・クローバー×リドル・ローズハート
※直接的な描写はありませんが、男性も妊娠・出産が可能な世界です。 ※これらと同一設定になりますが、これ単体でも読めると思います。
【1】
ある土曜日の午前中のことだった。
それはリドルが馬術部の当番で厩舎に入った時、トレイがキッチンでクッキーを焼いている時、ケイトがSNSで見つけたメイクを試したくて洗面室へと向かった時、エースとデュースが外泊していたオンボロ寮を出た時。“その時”、奇妙なことが起こった。学園内に、いるはずのない存在が現れた。
***
馬たちが戸惑っている。小さく息づかいに混ぜた鳴き声を上げたり、うろうろと首を動かしたり、小さく足踏みをして。リドルはその原因をすぐに発見すると、目を見張った。
「……! 誰だい、キミは……」
「………………」
空の馬房に、少女が一人眠っている。いや、倒れているのか。リドルは傍らに膝をつくと、様子を検分した。命に別状はなさそうだが、頬や膝には細かな擦り傷があって、服も馬房の土や藁とは別の何かで汚れている。体格や服装の雰囲気からしてせいぜいエレメンタリースクールほどの年頃だろう。
「大丈夫かい? キミ、こんなところで寝ていてはいけないよ」
「……う……ん……」
外からは見えないダメージがあるかもしれない。慎重を期して頭を揺らさないようリドルが声をかけ続けると、少女は寝返りをうった。まるで柔らかいベッドに寝ているかのように。さらさらとした赤毛の後頭部には、傷などはなさそうだ。リドルはごく優しい力で少女の肩を叩く。
「大丈夫そうだね。さあ、起きるんだ」
「うーん、まだねむたい……もう少し寝かせて、お父様……」
「寝ぼけるのはおやめ。ボクはキミのお父様などではないよ」
少女は身を起こしながら目を何度も瞬く。そしてやっと鮮明になった視界でリドルを捉えると——改めて「お父様!」と言いながら抱きついた。
「な……っ!? なんだい、キミは!? ボクはまだ十七歳で、キミみたいな子供がいるような身ではないよ!」
「こういうのあんまり言わない方がいいってわかってるんだけど、どうしたらいいのかわかんないの! だから言っちゃう! わたし、未来から来たあなたの娘だよ!」
「おかしなことをお言いでないよ! 困った子だね……大体キミはちっともボクに似ていないじゃないか」
「こんなヘンテコな癖毛、うちの家系だけじゃん!」
「へ、ヘンテコ……!?」
少女が指差したハート型の癖毛を、リドルは指でそっとすくった。ワックスなどでセットしている形跡はない。ウィッグやつけ毛でもない。
「あとは口元かなあ……わたしがお父様に似てるって言われるの……」
少女は目元を手で隠して口元を強調する。小造でつんとした唇は言われてみれば似ているような気もしたが、人間の顔の造形に疎いリドルにはよくわからない。
「どうしよ……どうしたら信じてもらえるかな……」
うーん、と考え込んだ少女がからし色の瞳を少しすがめたのを見て、リドルはハッとする。まさか。そんなはずは。
「……キミ、もう少しお顔をきりっとさせてごらん」
「こう?」
少女は大きな目と眉にほんの少し力を込めた。そうすると、あの時リドルを連れ出してくれた少年の、今右腕として側にいる方に、驚くほど似ていた。暖かいからし色の瞳を輝かせるのは、よく似た自由の光。
「——キミは、トレイに、似ているね」
「そうなの! わたし目元はパパ似だねってよく言われるの!」
「じゃあ、なおのことキミは嘘だよ」
リドルはふらつきながら後ずさって、少女から離れた。
「お父様?」
「また誰かが都合のいい幻を見せている? またボクは魔法領域の中にいる? いったいどうして……」
「待って待って、お父様! 嘘なんかじゃないよ!」
リドルを捕まえるように、少女はもう一度抱きついてきた。それを振り払おうとして、やはり躊躇ってリドルは立ち尽くす。リドルが周囲の同年代よりも小柄で華奢であるとはいえ、それよりも更に小さな少女を突き飛ばすのは簡単だったはずなのに。
「だって——だって、お母様がボクとトレイの結婚を許すわけがないじゃないか!」
「その辺は、まあ、孫から見てもかなりこじれてるんだけど……」
少女は心底複雑そうに眉根を寄せて苦笑いした。
「……それ以前に、トレイがボクを伴侶に選ぶ理由がないじゃないか」
「えっ!? あんなにパパにはお父様しかいないって感じなのに……」
少女は、トレイによく似た瞳でリドルを見上げている。目を逸らしてしまいたくなるのに、抱きしめる小さな身体の存在感が、それをさせなかった。
「自分のこと証明するのってすっごく難しいな……。とにかくわたし達は“いる”……いや、“今”はまだいないけど、いつかはいるんだよ!」
気がつけばリドルは少女の頬の傷についた埃をぬぐっていた。少女はその手を当然のように受け入れている。
「……ボクが、キミみたいな子がこんな風に甘えられる親になれるわけないじゃないか」
「お父様は厳しくて優しいよ。それが、わたしにとってのお父様——あなたなの……」
少女の腕からふっ、と力が抜ける。
「でも、あなたはまだそうじゃないんだね……」
毎朝ギリギリまで寝てしまうのを起こしてくれる、リビングで寝てしまった少女をベッドまで運んでくれる(“パパ”は絶対に起こして歯磨きをさせるのに!)、ピンとアイロンがけされたハンカチをポケットにねじ込んでくる、学校からのおたよりが鞄の底でくしゃくしゃになっているのを怒る、食べるのが遅くて食器が片付かなくても微笑んで待っていてくれる、寝る前に気高い馬のお話をしてくれる、そんななんてことない時間の積み重ねが、日々の思い出が、十七歳のリドル・ローズハートにはまだない。そして、それがある方のリドル・ローズハートにはもう二度と会えないかもしれない。そのことを実感して不安になったと、少女は震える声で言った。
「……キミが本当にボクの子か、別の意味で疑わしくなってきたよ……」
「そうなんだけど……そうなのかなあ……」
今にも泣きだしそうになった少女に、リドルは慌てて「でも!」と大きな声を出す。
「ひとまずキミのことを信じてみよう。そうじゃなければ部外者のキミが学園に入れた説明がつかないし、何か思い違いをしているとしても迷子は保護すべきだからね」
一転してトレイによく似た笑顔になる少女に、本当にそうだったらいいのに、と思ってしまったことは言わない。
「ありがとう! わたしの名前は——」
名乗ろうとした少女の口を、リドルはピシッと人差し指で塞いだ。
「言うのはおやめ。もしキミが本当に未来から来たのなら、今……キミにとっては過去か、この時代への影響は少ないほうがいい。そうだね……キミのことを仮に、“クイズ”と呼ぼうか。いいかい? ミス・クイズ」
「……うん! なんかかわいい響き!」
手でアルファベットのQを作って飛び上がる少女に笑みをこぼしながら、リドルは寝わら鈎を手に取る。
「さて、先に馬たちの世話を済ませてしまうよ。その間に事情を聞かせておくれ。じきに他の当番の部員もやってくる、それまで時間がない」
「わたしも手伝う!」
「いい子だね……ところで、キミはさっき“わたし達”と言ったけれど……」
「わたしにはお姉ちゃんとお兄ちゃんがいるの。そもそもこうなったのはお姉ちゃんが——」
***
「おはよ! どしたの?」
「ああ、ケイトか。大したことじゃないんだけど……」
ケイトはシャワー室で一人の三年生が「うーん?」と首をひねっているのに通りかかった。
「シャワーを浴びるのに、タオルがなくて。俺、確かにここにかけたはずなんだけど……」
「マジ? 浴びる前に気付いてよかったね。危機一髪じゃん!」
「やっぱ部屋にタオル忘れたんかな~。めっちゃ眠かったし……」
「かもね~。オレもたまに忘れ物することあるよ」
大したことのないやり取りを終えるとその三年生は自室へタオルを取りに行った。ケイトはそのまま洗面室へ入る。洗面室では寮生が一人、洗濯機を回していた。
寮生。そのはずだ。休日なのにルームウェアや寮服ではなくきっちりと制服を着込んでいて、腕には赤い腕章が巻かれている。しかし。
「ねえねえ、ちょっといい?」
「!」
振り向いた彼は身をこわばらせた。黒髪の少し重たげな前髪にセルフレームの眼鏡。電灯がレンズに反射して、瞳の色はわからない。この洗面室は、奇妙にも晴天の日の自然光のような光で照らされているのに。
ケイトの知らないハーツラビュル寮生。そんなものが存在するはずがなかった。
「君、うちのコじゃないよね? 変身系の魔法とか使ってる? ちょーっと一緒に来てくれるかな?」
ケイトはマジカルペンを握った。見たところ、彼は一年生程度の年齢に見える。立ち姿も無防備で、強そうには見えない。——しかしもし、見た目からは判断できないほど強力な魔法士だったら? 外部からナイトレイブンカレッジに侵入したのだとしたら、その可能性は低くはないだろう。だとしても、ケイトは退くわけにはいかなかった。ここは三年間過ごしたケイトの大切な居場所なのだから。
「……わかりました」
「……助かる~」
彼は大人しくうなずいて、空っぽの手のひらを肩ほどに上げた。内心ひどくほっとしながらも、ケイトは、その声が妙に誰かに似ていることが気になってならなかった。
「……驚いたな」
「うっそでしょ……」
寮内で騒ぎを起こさないために、奇妙な侵入者はひとまずトレイとケイトだけで預かることにした。ドゥードゥル・スートで変身魔法や認識阻害魔法の類いを上書きして解くと、現れたのはワインレッドの髪。謎の反射が消えたレンズの向こうには長い睫毛に縁取られたスレートグレーの瞳。誰かに——他ならぬリドル・ローズハートにあまりにも生き写しの顔立ち。特徴的な癖毛だけがない。彼がなぜ、何の目的でここにいるのかを問い質すのも忘れて、トレイとケイトは呆気に取られてしまった。
「……その、詳しい事情をお話しすることはできないのですが……」
おもむろに、彼の方から説明を始める。
「僕には無茶苦茶な姉と目の離せない妹がいて。ある日姉によって奇妙な冒険に巻き込まれたんです。汚れて傷ついた状態でここに辿り着いて、姉と妹とはぐれてしまって。二人を探しに行かなければいけないので、もうここを離れてもいいでしょうか? あの、タオルは持ち主の方に返していただけると助かります」
「……えーと……」
「……ちょっと待ってくれないか」
口調こそ控えめだが一方的な都合だけを通そうとする説明に、今度は別の意味で呆気にとられてしまう。
「残念だがNRCは、その説明で解放してやれるような場所じゃないんだ」
ケイトが感じた懸念を、トレイも同様に抱いている。彼がNRCに侵入した危険人物でない保証はないのだ。トレイは彼を警戒しながらも、ちらちらとキッチンの出入り口や窓にも視線を配っている。
一方でケイトは彼をじっと見つめていた。彼の顔、仕草、イントネーションをじっと観察する。そのうちに、ある馬鹿げた考えが身をもたげて、もっともらしくケイトの頭の中を歩き回り始めた。
それほど長くはない膠着を破壊して、ついにケイトはその考えを口から解き放つ。
「思ったんだけど、もしかしてハーツラビュルの寮生っていうのは嘘じゃないんじゃない?」
「どういうことだ?」
「うちの洗濯機って、わかりにくくて使いにくいので有名じゃん。オレが見つけた時、この子はそれをしっかり使いこなしてた」
壁に埋め込まれたまあまあ新しい型のドラム式洗濯乾燥機は、ボタン操作やドアの開閉にコツがいる。それどころか、初めて見る者ではボタンの場所すら見つけるのは困難だ。しかしケイトが彼を見つけた時、一番端の洗濯機は平然と回っていた。
「すっごくすっごく映画っぽいんだけど——もしかして君、未来から来た?」
「!? おいケイト、一体何を言い出すんだ!?」
荒唐無稽な説にトレイは目を見開く。ケイトは珍しく興奮した様子で椅子から立ち上がると、椅子に座らされた少年の顔を指さした。
「いやぶっちゃけ洗濯機のことよりも! この子、リドルくんにソックリじゃん! トレイもちゃんと直視しなよ!? さっきからチラチラ目、逸らしてんじゃん!」
「俺達よりも上手の魔法士が二段構えで見た目を偽ってるだけかもしれないだろ!」
「何のために!?」
「……俺達を……油断させるため……? だって——リドルによく似た未来人なんて、そんな……」
ちょっとした口論を、少年は縮こまりながら見つめていた。それをトレイはやっと直視する。もしもケイトの説が正しいなら、この子はリドルの血縁者——こんなに似ているのなら、おそらく子供だ。その可能性はトレイにとっては少し受け入れがたく、ケイトの説を聞く前から胸騒ぎがして直視することができなかったのだ。
「……ケイトさんの推察通りです」少年は深く息をついて、やっと真実を告げた。
「僕は、未来から来たハーツラビュルの一年生です。両親のことについては……あまり言い過ぎない方がいいでしょう。名前は……ええと……」
「じゃ、名前も言わない方がいいよね。君のこと、”セカンド”って呼んでもいいかな?」
「ケイト!」
「じゃあ”ジュニア”にする?」
思わず険しい目をしたトレイを、話が進まないだろ、とばかりにケイトは睨み返す。少年は「わかりました、”セカンド”で」とすぐさま仮の名前に同意した。
「さっきお姉ちゃんと妹ちゃんがいるって言ってたよね。三人まとめて誰かにこの時代に連れてこられた系?」
「確かに、警戒すべき敵がいるのかは重要だな」
少年は端正な顔を歪ませて、非常に苦い顔をした。「それは……うちの姉です」
「……どういうことだ?」
「……えーっと、もしかして、ヤバイお姉ちゃんなの? ケンカしてるだけとかじゃなくて?」
ケイトの問いに、少年は大きな声を上げる。「うちの姉は天才で、イカれています!」
「い、イカれって……」トレイとケイトは思わず少しのけぞってしまう。
「かつては真っ当に史学と考古学を専攻していたはずなんですが、いつの間にか過去に行く魔法にのめり込むようになって……! 時間軸に干渉しうる魔法は、僕の時代では禁止されているんですよ!」
「俺たちの時代でも多分禁止されてると思うぞ……」
「そして姉は高校生の時に失踪して……三年ぶりに、ハロウィーンの一般開放日に妹を連れて僕のところへ現れて——『準備ができたよ、着いておいで』なんて言い出した時から嫌な予感はしてたんですよ!」
「そ、それでお姉ちゃんの魔法でこの時代に来たの?」
「いいえ! たくさんの信じられないものを見ました——タイムポリスとか、タイムポリスが管理するデスゲームとか——巨大な赤ちゃんの姿をした時間を司る超存在を見たことがありますか!?」
「うわ、シュールで映えそ~、自分事じゃなかったらだけど……」
「すごい冒険をしてここに来たんだな……」
「もう冒険はたくさん! とにかく僕は姉と妹を連れて帰らなきゃいけないんです! 両親が、みんながどんなに心配してるか……」
その種の責任感は、トレイにとっては他人事ではない。ここまで張り詰めてはいないにしても。トレイはやっと、セカンドの振る舞いに”真実”を感じ取ることができた。
「姉が言うには、タイムポリスもタイムベイビーも時間という概念の一側面でしかないらしくて……それでもあえてその管理者に勝負を挑んだのは、彼らが有する”時の願い”というものを手に入れたかったからだそうです。それを使えばどんな願いも叶うとか……」
「いかにもマクガフィンって感じ〜」
「お姉さんはどんな願いを?」
「それはわかりません。けれどきっと、ろくなものではないでしょう。それが姉の手に渡る直前に、癇癪を起こしたタイムベイビーに僕らはこの時代に飛ばされて、”時の願い”は……」
「「”時の願い”は?」」
二人して身を乗り出す。セカンドは目を伏せてため息をついた。
「……わかりません。最後に妹が手を伸ばしているのが見えたような……」
「——もしも君の妹さんが確保しているのなら、それを使って元の時代に帰れるかもしれない。それに賭けて、お姉さんより先に妹さんを保護しよう」
「闇雲に探そうってわけじゃないんでしょ? 君が最初にしようとしてた作戦、協力するよ!」
「ケーくん、パ……トレイさん……!」
セカンドは顔を上げて、少し表情を緩めた。ケイトは「今の聞こえた?」とこっそりトレイに耳打ちする。
「こんなに警戒心の強そうな子にもう”ケーくん”なんて呼ばれて、お前は本当に人たらしだな」
「そうじゃなくて……あー、もういい」
トレイがわずかな呼び間違いには全く気が付かなかった様子なのでケイトは完全に呆れてしまう。セカンドの方へ向き直ると、セカンドはキーケースから古びた一本の鍵を取り出すところだった。柄にはナイトレイブンカレッジの校章が刻まれている。その点でも、彼がNRC生であることは間違いなさそうだ。部室など校舎の一室の鍵を生徒が預かること(または、こっそりと合鍵を作ってしまうこと)は珍しくない。
「僕、放送部に入っているんです」
リドル・ローズハートによく似た声で、少年は言った。
***
デュースが教室に課題のノートを忘れたと言うので、四人はメインストリートを歩いていた。ハートの女王の前に立っていた背の高い人影を遠目に「誰だあれ? うちの生徒じゃないんだゾ」とグリムが声を上げた。女王を見上げているのは、確かに長い髪の若い女だった。
「お姉さーん、なんか迷ってます?」
気さくな笑みを貼り付けてエースが声をかける。振り向いた女は長い一部を残して頭部の大半を刈り込んでいた。レザージャケットの袖からはタトゥーが覗いている。スニーカーの厚底を差し引いても、エースやデュースよりも背が高い。耳や口許には銀の鋲や鎖のピアスがじゃらりと揺れている。それに気づいてエースは若干おののくが、顔には出さなかった。
「あの、今日は一般開放日じゃないですけど……」
言葉を引き継いだデュースと、他の三人に女はにっこりと微笑んだ。それは穏やかなはずなのにどこか攻撃的で、監督生は肩に乗るグリムの毛がそわりと逆立つのを感じていた。
「こんにちは。私は大学で歴史を研究しているんだ。ここの図書館にしかない文献に用があってね。それにNRCの校舎自体も研究対象として申し分ないよ。おま……君たちはこの校舎がいつからあるか知っているかな? 知らないんじゃないかな? 先程ディア・クロウリー校長も嘆いておられて……」
「こいつすげーグイグイ喋るんだゾ!」
「今一瞬お前って言いかけた?」
「まさか! 初・対・面でそんな無礼を働くわけがないだろう! 私はこう見えて薔薇の王国出身の淑女さ」
確かに女の首には”GUEST”と印字された入館証が下がっている、と監督生が指摘した。監督生の手を引っ張って女から少し距離を取ると、四人は頭を寄せ合う。「同郷か……」「でもな〜んか……」「怪しいっていうか……」「雰囲気がこえ〜んだゾ……」「よく見りゃ顔立ちは整ってるけど、ファッションがいかつすぎ……」「エースはこういう人が好みなのか?」「そうは言ってねーだろ」
特に”よそ者”への警戒心が強いエースだけでなく、自身も異物である監督生以外全員が不安を感じ取っている。その間女は目をすがめて時計塔を見つめていた。
ヒソヒソ話の輪を一人抜け出した監督生が、特にどの歴史を研究しているんですか? あるいは、ツイステッドワンダーランドの歴史全然知らないや、と女に声をかけると、女は「よくぞ聞いてくれたね」とグレートセブンを一人一人指差した。長い腕を伸ばして、大きな直径で回るように。
「私はグレートセブンを研究しているんだ」
「グレートセブンって……偉人中の偉人だし、研究され尽くされちゃってるんじゃね?」
「そうだね。確かに彼女・彼らの偉大さは知れ渡っているとも」
エースがすくめた肩を女はがっしりと掴み、「うわ!」と小さな悲鳴を上げさせる。そのまま女の顔を見上げたエースの顎を掴むと、他の三人の方へその顔を向けさせた。
「例えばだよ、エースが何かを成し遂げたとしよう。紙幣に肖像が印刷されるほどの偉業だよ。もしかしたら君を模範とする学校だって建って、そこにはこんな風に銅像が立つかもしれない。ポーズはどんなものがいいかな? 空港の名前にだってなるかもしれないね。エース・トラッポラ記念国際空港だよ! そのように偉業には、成し遂げた者の名前がついて回るものなんだ。では——この中に、ハートの女王の名前を知っている人はいるかな?」
「……えーっと……」
「それは……」
女はエースを解放すると、次はデュースの肩を抱いた。
「君たちはハーツラビュルの寮生なんだろう? ハートの女王の法律は守っているのに、その本名も知らないのかな? 砂漠の魔術師や海の魔女の本名でも構わないよ!」
「っ……」
狼狽し視線を彷徨わせるデュースを解放すると、今度はグリムを抱き上げた。「ふなー! 放すんだぞ!」と白目をむいて暴れるグリムの毛並みを撫でながら監督生に向き直る。
「これはね、エースやデュースがものを知らないんじゃないんだよ。ツイステッドワンダーランド中がそうなんだ。グレートセブンには不可解な点がまだまだ多すぎるのに、どういうわけかみんな途中で研究をやめてしまうんだ。私はそれを明らかにしたい、真実を知らしめたいんだよ。世界中にね!」
監督生は、秘密なのには理由があるかも……と言った。あるいは、沈黙のまま、内心鏡の夢で見た姿は……と思い出していた。しかし女はそれを一笑に伏した。
「君は世界が沈黙に耐えられないかもしれないと心配しているのかな? でもね、真実ごときに耐えられない弱さはいらないんだよ」
「……そういうつよーいアンタは、誰なんだよ」
エースが女の手からグリムを半ば奪い取るように受け取ると、デュースが監督生を守るように立ちふさがった。
「私は……私はドミノ・クロックズ。時を揺るがす歴史研究者さ。——そのうちにね」
エースとデュースと監督生とグリムはまたヒソヒソ話をした。この女を放っておいてはいけない。見張っていたほうがいい。四人は顔を見合わせた。エースは先陣を切って顔に笑みを貼り付ける。
「話聞いてたら歴史に興味出てきちゃったな〜! ついて行ってもいいですか?」
いいとも、と気さくに笑ったその顔が、デュースには誰かに似ている気がしてならなくて、一方エースはいつドミノの前でフルネームを名乗っただろうかと訝しんだが、結局二人とも何にも思い至ることはできなかった。