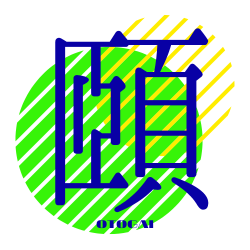※元ネタあり捏造生徒が大人のトレリドに失恋する話です。 『悪魔バスター★スター・バタフライ』31話『最高の一日』37話『失われた本』を見て頂ければより一層お楽しみいただけます。 トレリド子育て時空ですが、これのみでも読めると思います。
L少年には大勢のきょうだいがありましたが、その中で黒い馬車が迎えに来たのは彼一人だけでした。そのことにあからさまな優越感を覚えながらも、産まれ育った“ここ”ではない“どこか”へ行けるということは、L少年を不安にもさせました。学校に通ったことはほとんどなかったし、棺の中は信じられないほど静かで、両親の罵声やきょうだいたちの騒ぎ声から初めて切り離されて、まるで自分が本当に死んでしまったようだと思ったのです。
棺から出されて、ちびで痩せぎすのL少年は新入生の群れの中で転倒しました。勿論これからナイトレイブンカレッジの同輩となる他の少年たちは誰も助け起こしてはくれません。
着せられた式典服の裾を踏みながら、少年がやっと立ち上がろうとしたその時です。
「キミ、大丈夫かい?」
薄暗い廊下の中で、見たこともない真っ白な服——それはL少年が知らないだけで、何の変哲もない白衣とシャツだったのですが——を着た大人が一人、L少年の前に屈んで、手を差しのべてくれました。
(キレイなひとやなあ。なんでこの人はこっちに手を伸ばしてるんやろ)
「早く鏡の間へ向かわないと、入学式が始まってしまうよ。それとも、具合が悪いの? 棺の中で酔う事例は稀にあるけれど……」
「へえっ!? あっ、そのっ……」
「うん、意識はしっかりしているね。さあ立って」
赤い髪をしたその大人は、慌てて立ち上がったL少年のフードをかけ直すと、廊下の向こうを真っ直ぐ指しました。
「遅刻は許されないよ。お急ぎ。けれど廊下は走らないように」
「は、はひっ」
「ああ、それから——入学おめでとう。キミの4年間が有意義なものであるよう祈っているよ」
その細い指は、L少年の人生に初めて現れた道しるべでした。
***
「せーんせっ! またケガしてもうてん、治してぇ~」
「アヴァドン、喧嘩は控えるようにと言っただろう?」
「ちゃうねん! 向こうがいきなり殴ってくるんや!」
家庭に居場所というものがなかったL少年は、残念ながら寮生活でも居場所を得ることができませんでした。人より大幅に遅れた勉強も、発育不良でエレメンタリースクール生程度しかない体躯も、絞りカスのように薄い妖精族の血統を受けてほんの少しだけ人と違っている容姿も、不利の材料にしかならなかったのです。
L少年ははじめての喧嘩で大敗して担ぎ込まれた保健室で、入学式の時の“キレイなひと”が校医のリドル・ローズハート先生だと知ると、そこを逃げ場にして入り浸るようになってしまいました。少しのケガでも駆け込み、仮病を使っては追い返されを繰り返す始末。治療を受けるために他の生徒を挑発するまでになってしまいました。
「何度も言うけれど、馬鹿な真似はおやめ。保健室も出入り禁止にしてしまうよ」
「ひィ! 堪忍してください!」
L少年の行動はローズハート先生にとって大きな悩みの種ではありましたが——学園に来て初めて甘えられる大人に出会えたのだとわかるときっぱり突き放してしまうこともできず、つい勉強を見てやったりしてしまうのでした。そもそも保健室はナイト・レイブン・カレッジでは数少ない安全地帯で、生徒たちの健康を守ることはローズハート先生の責務。肉体的にであれ、精神的にであれ、困難を抱えて救いを求めてきた生徒を拒むことなどできません。
「何でオレはディアソムニアに入れんかったんやろか」
少年はディアソムニアの生徒に対してはとりわけ頻繁に突っかかっていました。そこには、自分がディアソムニアには選ばれなかったことのコンプレックスのようなものが見て取れました。
「寮は闇の鏡が魂の資質を見て決めるものだよ。キミのなかに、きっとサバナクローらしい不屈さがあるのじゃないかな」
「せやけど……オレのひいひいひいひいひい祖父さんはディアソムニアやったんやて。その血がディアソムニアの部分と違うんやろか」
L少年の父親の数少ない誇りが、6代も前の祖先でした。真っ当に異国の学校を出て、出た後も偉大な魔法使いに師事し、その後地元のはぐれ者達を雇って商売を興し、ひと財産を築き上げたらしい人。今となってはその遺産を食い潰すばかりで、栄光の輪郭しか伝わっていない人でした。
「……親が——祖先がどうであるかよりも、闇の鏡はキミ自身の魂の形を見ているよ」
「ふうん……?」
L少年は何も響いていない様子で首を傾げました。先生はこの少年のことを、目の開いたばかりの赤ん坊のようだ、と内心評していました。子供にとっては途方もなく巨大なしがらみの中に溶けていた状態からいきなり切り離されて、周囲はおろか自分自身のことすら見えていない。言動への現れ方こそ違えど、それは幼い全能感に溺れかけた日々を思い出させるには十分でした。
NRCに勤務して数年目、問題を抱えた生徒は何人も見てきましたが、L少年はとびきり骨の折れそうな生徒です。ですがやることは変わりません。校医として、その子に必要なものを与えるだけです。
「ところで、アヴァドン」
「な、何!? せんせ——」
ローズハート先生はいきなりL少年の顎を掴みました。怖い顔でじっと見つめられて、L少年の鼓動は早鐘のようでした。
「……キミ、この前の健康診断で歯科に行くよう指導したはずだよね? まだ行っていないの?」
「だ、だって歯医者なんか行ったことあらへんもん! 怖いし——」
L少年の顎をパッと解放すると、ローズハート先生はスマートフォンで何事かメッセージを打ちこんでこう言いました。
「紹介状と闇の鏡の使用許可を出してあげるから、週末必ず行くように。おわかりだね?」
怖いから歯医者に行ったことがないのか、歯医者に限らず病院というものにほとんど行ったことがないから怖いのか、L少年にはわかりませんでした。けれど、週末行かなければならないらしい歯医者も、ローズハート先生みたく優しいとええな、と思いました。言葉こそ厳しいけれど確かな優しさを、ローズハート先生からは受け取っていた気でいたのです。これから初めて会う大人に対して不安や恐怖以外の期待を抱けるのも、その優しさのおかげでした。
***
「リド——ローズハート先生から話は聞いてるよ。歯医者は初めてなんだって? ほら、そこにかけて、口を濯いで」
「ゆすぐ?」
「ぶくぶくして、ぺってするんだ。——よし、椅子を倒すぞ。椅子の上の方に上がって……そう、頭がこの辺りに来るように」
緑色の髪をした歯医者は、L少年の幼い物言いに呆れ顔一つせず、それどころかにこりと笑いかけてくれました。ローズハート先生ですら滅多に笑顔を見せてはくれません。口の中に様々な見たこともない器具が差し込まれるのは怖いし、歯石を取るのは痛かったけれど、「頑張れ、あと少しだぞ」と柔らかく声をかけられていると、その痛みが無為なものではないと信じることができました。それはL少年が初めて感じた“安心”でした。
「ちょっと虫歯は多いけど、取り返しがつかない段階にはなってないな。保険が効くうちに来てくれてよかった。虫歯の治療は次回以降していくとして、今日は歯磨きのやり方だけ見ていこうか」
手渡された歯ブラシを握る手には力が入ってしまいます。歯医者はそれをそっとほどいて、優しく握り直させました。
「こんなんで汚れ取れるん? 強く擦った方がちゃんと取れるんちゃう?」
「力を入れすぎると歯の表面や歯茎を傷つけるからな。自分で自分の口に優しくしてやるんだ」
「ほへへ……」
「この鏡をよく見て、一本一本優しく丁寧に磨いて……君は嘴があるから……嘴と歯の間の汚れはしっかりと掻き出すんだぞ」
“優しさ”というのはただ乞うだけで、それでも得られず、自分から何かに、特に自分に対して与えられるものだとはL少年はそれまで知りませんでした。小さな丸い手鏡の中の黄ばんだ歯は、ただ当たり前にその色をしているだけのものだと思っていました。ですが実際には、他でもないL少年自身が見て見ぬふりをしてきたがためにそうなったものだったのかもしれません。それを歯医者は少しも叱らず、これから良くなっていくさと笑うのでした。
「その鏡と歯ブラシと……あとこの歯みがき粉をやるから、寮に戻ってからも磨く習慣を作っていくんだ。毎晩必ず、寝る前に」
「さっきやったみたいに糸とか通さんでええんか?」
「本当はやった方がいいんだが、最初のうちは習慣を作るのが大事だからな。あんまり手順が複雑だとうんざりするだろ?」
「そんなん——いや、せやろか」
「慣れたらでいいんだ。もっと手を掛けたくなったら手段を増やしてみてくれ」
「……へぇい」
「気になるなら複数回磨いてみてもいい。特にターキーなんかを食べた日の夜は二回磨いた方がいいぞ」
「なんでぇ?」
「美味しいものは虫歯菌にとっても美味しい栄養分だからな。気をつけ過ぎるってことはないぞ」
会計の後、歯医者はL少年の手に緑のセロハンに包まれたキャンディを握らせて、「また来週」と微笑みました。その場で口に放り込むと、ミントの清涼感と蜂蜜の甘味がL少年の口の中に広がります。口の中の飴と一緒に警戒が溶けていくのを、L少年自身も、歯医者も感じ取っていました。
終始微笑んでいた歯医者に見送られて外に出た少年は、初めて訪れた薔薇の王国の閑静な住宅街をほつき歩いていました。口の中の飴がすっかりなくなってしまうまで。
***
「ちゃんと行ったで!」
「よろしい。次回以降もちゃんと忘れずに行くように」
誇らしげに見せつけられた診察券。ローズハート先生はそこに印字された次回の予約日程を細い指でなぞりました。そして、『L・Avadon』の表記にはたと目を留めます。
「キミ、本当にこの名前でいいのかい」
「オレの名前はこれしかないねんで?」
「キミが望むなら改名することもできるし、そのためには使用実績を作っておくと有利だよ。——アルファベット一文字でいなくてもいいんだ」
「できるんか、そんなん……」
驚きと戸惑いでいっぱいの目で、少年は手の内の診察券を見つめました。両親が適当に名付けた何の意味もない一文字は、なぞるというには短すぎて、少年の指はその周りを何度もぐるぐると回ります。
「うーん、せやったら先生がつけてくれへんかなあ」
「自分で名前を選べるなんて、滅多にないことだよ。キミがしっかり考えるべきだ」
「でも……でもオレ、わからへん……」
自分に一文字以上の価値があるかどうかということが。それが少年にとって唯一の尊敬する大人から授かるものなら、どんなものでも喜べるのに。
「そうだ、今日は辞書の使い方を教えてあげよう。図書館から一冊借りておいで」
「わ、わかった! ほな行こか!」
「何を言っておいでだい。ボクは保健室を留守にするわけにはいかないよ。キミ一人で行くんだ」
「ええ~!」
「不平はおよし。わからなかったら常駐している……している、はずだ。司書にも尋ねてごらん」
ローズハート先生はそう言って少年を保健室から出してしまいました。内心、少しは他の大人との信頼関係も築けるといいのだけれど……という憂いもあって、そのためにまず司書を頼らせるのは悪くないように思えました。結局、この後すぐにL少年は少し版の古い辞書を抱えて戻ってきて、その目論みは失敗に終わりましたが。