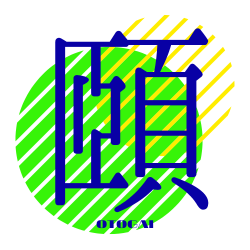トレリドと『なんだかんだワンダー』のクロスオーバーです。 #TreyRidWeek2025 に参加させていただいた作品d 7日目のお題「クロスオーバー」で書かせていただきました。 素敵な企画ありがとうございました!
宇宙を漂うシャボン玉がぱちんと割れて、その旅人達はナイトレイブンカレッジへと落っこちた。
「やれやれ、オーブルジュースが割れるなんてどういうことだい? ワンダー、早いとこもう一度張り直して出ていこう……ワンダー?」
馬に似た旅人の丸みを帯びた青い身体は、揃いの黒い制服を着た集団に飲まれてしまった。今がナイトレイブンカレッジの下校時間だということは知る由もない。「ちょっと! 通しとくれ!」肩がぶつかり、舌打ちをされ、思わず野蛮な部分が顔を出してケンカを買いそうになるが、相棒のためとグッと飲み込む。そのタイムラグで、すっかり相棒を見失ってしまった。
「どうした? 迷子か? 鏡舎まで来てしまうなんて……すぐに厩舎に送り届けよう」
「シルバー!? 貴様の目は節穴か!? これはどう見ても馬術部の馬では……というか馬かこれは!?」
黄緑色の腕章を着けた銀髪の青年が唯一それを気にかけて立ち止まる。それを意に介さず、彼女は人混みの向こうに叫び続けた。
「どいとくれ、相棒とはぐれそうなんだ! ワンダー! ワンダー!!」
そんな彼女の相棒は、一人の生徒が買い物袋から落としたオレンジを拾って、トランプの飾りのついた鏡に飛び込んでいった後だった。
「ねえねえー! これ、落としたよ!」
「ああ、ありがと……えっ?」
オレンジ色の毛むくじゃらに、若草色の山高帽。ライン入りの白靴下にスニーカー。大きさは腰ほどだろうか。謎の生き物にエースは目を見張る。
「えっ……えっ、ええっ!? 何……!?」
その問いかけも聞かず、毛むくじゃらは高い所の薔薇を塗るデュースのところへとすっ飛んでいくと、ぐらつく脚立を支えた。
「危ないよ! 気をつけてね!」
「ああ、助かる……えっ!?」
「待て待て待て、お前誰だよ!? っていうか何!?」
「ぼくはワンダー! 旅をしてるんだ!」
にっこり笑って自己紹介をする毛むくじゃらに、二人は絶句する。薔薇を塗り終わったデュースを「危ないからね! 終わったら降りよう!」と脚立からひょいと下ろすと、ワンダーは辺りを見回して「わあ~~~~~!!」と歓声を上げた。
「これからパーティーするの!?」
「あ、ああ……そうだけど」
「みんな準備に忙しそう! 手伝わないとね!」
ワンダーはなぜか嬉しそうに飛び上がると、つむじ風のようにあちこちを手伝って回った。落ちそうなガーランドを引っかけ直し、テーブルクロスをピンと張り、茶器を運ぶ列に加わり……。
「お、おい、もしかして何か企んでる!? 言っとくけど、報酬とかお菓子くらいしか出ないからな!」
「報酬なんていらないよ~! 親切は大事だからね♪」
あまりの考え方の違いに、思わずゾッとするエースを置き去りに、ワンダーは寮内へも飛び込んでいった。デュースは呆然と首をかしげる。
「なんなんだ……? アイツ……?」
「ええと……ワンダー、だったか。手伝ってくれてありがとうな」
「料理もケーキもとっても美味しそう! 手伝えてすごく嬉しいよ! あ、サンドイッチはもう少しからしを効かせた方がいいと思うけど……」
「ああ、俺があまりからしが得意じゃなくてな。味見ができないんだ。からし入りのも追加しといてくれるなら助かるよ」
「オッケ~!」
トレイの作るサンドイッチよりも大振りのサンドイッチ達が、ケーキスタンドを少しはみ出しながら並べられる。
「お礼に何か一つつまみ食いしていいぞ」
「本当に~!? やったあ! じゃあこれにする!」
「あっそれは——」
「トレイ、寮内に不審な生き物がいるとの報告が——」
キッチンの扉が空いたのは、丁度一番特別なイチゴタルトがワンダーの喉を降っていった後だった。
「ハートの女王の法律第89条『女王の許しなしにタルトを先に食べてはならない』! ワンダーだったね、ハーツラビュルの女王であるボクの許しなくタルトを貪った、この罪は重いよ!」
「ええ~っ!?!? ごめんねぇ、知らなくって……! 本当にごめん、一番素敵で美味しいタルトをきっと楽しみにしてたよね……!」
「そこの焼き菓子のつもりだったんだが……言い方が悪かったな」
大袈裟なくらいに詫び続けるワンダーの首に、リドルは怒りの形相で杖を突きつける。
「この償いはしてもらうよ。キミが代替のタルトを作るんだ! さもなければ首をはねてやる!」
「でもリドル、そろそろパーティーを始めないと……。それに部外者をあんまり長く引き留めて置けないんじゃないか。首をはねるのも……」
トレイの提案に、リドルはウギ……と唸ったが、対してワンダーは何かを閃いて飛び上がった。被っていた帽子を恭しく取ると、リドルに向かって差し出した。
「じゃあ女王様、ぼくのこの帽子を貸してあげる!」
「……こんな帽子がなんだっていうんだい」
「これはどんなものでも必要な物を出してくれる魔法の帽子なんだ。素敵なパーティーには絶対にとびっきりのタルトが必要なはずだからね!」
リドルは不審げに帽子に腕を突っ込む。帽子は見た目の深さを無視してリドルの腕を飲み込んでいった。慎重に探ってリドルが取り出したのは、ハートのシールがついたレターセットだった。
「……なんだい、これは。これはどんなものでも出してくれる帽子じゃあなかったのかい。キミ、トリックでボクをからかったんじゃあないだろうな……」
「そんなまさか! うーん、でもこの帽子が出してくれるのは『欲しいもの』じゃなくて『必要なもの』なんだ。きみは誰かに何か手紙を書く必要があるんじゃなあい?」
逆さにして強く振っても何も出てこない。もう一度腕を突っ込むと、今度出てきたのは、ラブソングの楽譜だ。
「わかった! 帽子はきみに愛♡ を伝えた方がいいって言ってるんだ!」
「なっ……ふざけるのはおやめ!」
もう一度。今度出てきたのは麓の映画館でかかるデートムービーのチケットだ。
「リドル、もういいんじゃないか? ワンダー、帽子が壊れてるってことはないのか?」
ワンダーが代わりに腕を突っ込むと、トレイが作ったものによく似たイチゴタルトが一台出てきた。
「帽子は壊れてなんかないよ。うーん、同じものを出しても、帽子が出したんじゃ違ったものになっちゃうからじゃないのかな」
「……どういうことだい?」
「帽子が出す時点で、きみにとっては、トレイのタルトの代わりになんかならないってこと……きみにとって必要なのは……」
ワンダーは帽子からバンジョーを取り出すと、ロマンチックなコードをティロン……、と奏でた。「おやめ!」二音目を奏でる前に、水弾の魔法で壁際まで吹っ飛ばされる。湯気が立つほど赤面したリドルが、呼吸を荒くして魔法を放ったところだった。
「……さっきは悪かったね」
「いいんだよ! それよりタルトのこと、もう怒ってない?」
バスタオルにくるまりながらパーティー会場のすみでにこにこと立っていたワンダーに、リドルはひっそりと話しかける。
「きみは部外者で知らなかったということだし、代わりのタルトを出してくれたからね。ルールさえ守っていれば、パーティーを楽しんで構わないよ」
「やったあ! ところでこれって何のパーティーなの? きみの誕生日?」
「これはなんでもない日のパーティーだ」
「ななななんでもない日のパーティー!?!? すごいすごい、最高だね!」
「キミは本当に何も知らないで手伝っていたんだね……」
呆れて笑顔になってしまうリドルに、ワンダーはもう一度帽子を差し出した。リドルはそれを微笑んで受け取らない。
「悪いけど、何が必要かどうかは自分で決めたいんだ」
「……よーく知ってる相手で、すごく特別で、すごく好きなんだね」
「そうなんだ。まだこのままでいたいかもしれないし、早く伝えたい時もある。……歌は歌わないだろうけれど」
ワンダーは歌うと楽しいのに、と言いながらバンジョーをかき鳴らして、パーティーの中心へと歩いていった。そこへ、馬に似た旅人がやってくる。
「やれやれ、やっとワンダーを見つけられたよ……まーた人助けしてたのかい」
「そうだね、彼は随分パーティーの準備を手伝ってくれたと寮生達が言っていたよ」
「あんたもワンダーに助けられたのかい?」
「いいや、ボクは違うけれどね」
「じゃあ暴走したワンダーに迷惑かけられた? それは申し訳ないね」
「まあ、そうだね。……でも今は、そんなに怒っていないよ」
焦りはしたけれど、お節介焼きのせいで、今トレイを好きでいるということに喜びと楽しさを実感していた。それが、罪人ワンダーがもたらした償いだった。リドルは、不思議と笑顔になってしまう。