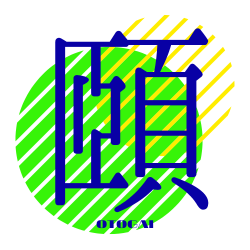2月14日の放課後、L少年は言葉にならない悲鳴を上げながら予約よりもずっと早く来院しました。運のいいことにその時他の患者はおらず、歯医者はぎょっとしながらも泣きじゃくる少年を裏の休憩室に座らせると暖かい紅茶をいれてくれました。シュガースティックとミルクポーションを添えて。
「どうした? 俺でよければ話は聞くぞ?」
泣き止まないことには治療ができないという理由もありましたが、歯医者は隣り合う椅子に座ると、L少年のしゃくりあげる呼吸が一定になるのを穏やかな笑みを浮かべて待っていました。
「チョコ……! 受け取ってもらえへんかったぁ……!」
「……そうかー……」
「き、『キミをそういう対象として扱うことはできない』ってぇ……せんせぇ……」
「ああ……」
「あ、愛してるのにぃ!」
「あ、愛?」
その幼い容姿と振る舞いから、歯医者はどうしても少年に対してエレメンタリースクール低学年のように接してしまうのですが、やはりれっきとしたティーンエイジャーだったようです。恋もするかもしれないし、それゆえに依存を恋愛感情に直結させてしまう、高校生なりの幼さを持っています。
「他のやつは受け取ってもろてたのに……試作や言うて……理由でっちあげて……ズルいわ……」
「その子たちは告白してないからじゃないかな……。君はその”先生”とどうなりたかったんだ?」
少年は黙り込んでしまいました。ずっと水面を見つめていた紅茶を一口すすって、二口すすって、砂糖を増やして、マドラーでかき混ぜながら、やっと口を開きました。
「……わからへん」
「わからないなら、きっと君の告白は気持ちを伝えることだけが目的だったんだな。告白しなかった子たちと違って、君は目標を達成して終わらせられたんだ。……偉いぞ、よく頑張ったな」
止まっていた涙がまたあふれ出して、ぽたりと紅茶に落ちます。
「その先生はきっとそんなことは慣れっこのはずだから、明日からはきっと元通りになれるさ。二度と保健室に来るなとは言われてないんだろ?」
「でもオレ……なんや恥ずかしい……」
少年は初めて”恥ずかしい”という気持ちを知りました。明日保健室に行くのが気が重いし、保健室以外に居場所が無いので登校すらしたくない。かといってサバナクローの四人部屋だって気の休まる場所ではない。恥ずかしいと言えば今ここでさんざ泣きわめいていたのもそうで、治療を放り出して逃げ出してしまいたい気持ちでいっぱいでした。つまり”恥ずかしい”というのは、自分の存在を拒絶したくなることなのかもしれません。
「このチョコどないしよ……」ひとまず今一番厄介な”存在”に少年は気を逸らしました。「どんなチョコを選んだんだ?」と興味深げな歯医者に保冷バッグを突き出します。
「お、賢者の島のパティスリーがミステリーショップにおろしてるチョコプリンじゃないか。これ濃厚で美味しいんだよな。いいチョイスだ」
「そうなん?」
「なんだ、食べたことなかったのか? じゃあ君が食べるといい。治療の準備に少し時間がかかるし」
そう言って歯医者が行ってしまうと、少年はプリンの蓋を開け、スプーンを突き刺しました。確かに、美味しい。けれど一口食べるごとに、本来届けたかった相手の手に渡らなかったことが思い出されてまた涙ぐんでしまいます。それでもやっぱり美味しい。失恋の悲しみとただただ美味しい快楽のどちらが強いのか、プリンがその存在を無くしていくごとに、段々わからなくなっていきました。ただ、『キミをそういう対象として扱うことはできない』という毅然とした声だけが、頭の中でぐるぐると回っていました。
その後のクリーニングと治療を終え、少年は初めて待合室のキッズスペースで子供が一人遊びをしているのに気づきました。泣き叫びながら駆け込んだ時もいたでしょうか。きっといたはずです。少年が自分の悲劇で頭がいっぱいで気づかなかっただけで。子供は、緑色の髪にグレーの瞳で、夢中で高く高く積み上げているブロックを見上げています。
「あれはうちの子だよ。俺の仕事が終わるまでそこで待ってるんだ」
いつものようにキャンディを握らせながら言った歯医者はプラチナの指輪をネックレスに通していて、L少年はローズハート先生の薬指にも同じようなものがはまっていたことを思い出します。一般常識に疎い少年が、恋(と自分では思っているもの)をして、初めて得た知識。
「……先生って、ローズハート先生のダンナさんか?」
「え? リドルから聞いてなかったのか?」
少年は、”恥”というものを今度こそ知ったと思いました。どんなに消え去ってしまいたい、自分の存在を消し去ってしまいたくても、そんなことは許されないということなのだと。抱えて歩かなければいけないものなのだと。
***
七月になっても、相変わらず叫びたくなるような時はたくさんありましたが、歯医者の言った通り、元通り生活を一日ずつやり過ごしていました。自分の甘ったれた振る舞いを恥ずかしく思うことはあっても、勉強を教えてもらえることはやはり嬉しかったし、その意欲が恥を忘れさせてくれました。
「……うん、これで入学前に必要だった学力はほとんど補完できたはず。ここまでよく頑張ったね」
「へへ! ローズハート先生のおかげや!」
特製の補習テストの束は随分と整ったものになっていて、少年は己の変化に思いを馳せました。あの棺に入って出て、本当に死んで生まれ変わったみたいや、と積み重ねた過去を誇らしく思いました。まだ一年も経っていないのに。
「これから夏休み中の時間を使って一年生の授業内容をしっかり復習しておいで。そうすればみんなに追いついて二年生を始められる」
L少年はあまりにもちっぽけで、未来のことなど考えたこともありませんでした。ただ、長い果てしない道をひたすら右足と左足を交互に動かすように生きていれば、自然とどこかにたどり着いているというようなものだと、漠然と捉えていました。だから、ローズハート先生が次に告げた言葉は、道がぷっつりと途切れてしまっているような衝撃を与えました。
「ボクはもういないけれど、わからないことがあればちゃんと職員室に聞きに行くように。他の先生にもよく話しているからね」
「え……?」
「キミは実践魔法に興味を持って、よく練習していたね。好きなことばかりではなく、苦手なこともしっかりやるように。けれど二年生からは実践魔法の授業も増えて、きっと楽しくなるはずだよ。だからしっかり備えるんだ。それから……」
「ちょ……待ってぇ……どういうことや!?」
ローズハート先生はしまった、という顔をして、自分の身体に視線を落としました。
「……産休に入るんだよ。でも、そもそもキミはボクに依存しすぎている。もっと他の先生や職員の方々にも頼って……友達を、作らないと」
「なんでそないなこと言うんや!?」
L少年の心は入学当初よりもずっと安定していましたが、L少年がローズハート先生一人に依存しているのでは、到底自立しているとは言えませんでした。ローズハート先生には生涯のパートナーとなる人がいました。それだけではなく、生涯の友人や、騒がしい後輩たちも。それと同じように、L少年にも拠り所を増やしてほしかったのです。
「嫌や! 先生……見捨てないでぇ……!」
「見捨てるわけじゃない! キミにとって大事なことなんだ!」
少年は泣きじゃくりながら床にうずくまってしまいました。周囲にあった椅子や衝立が浮かび上がります。少年が初めて使えるようになった魔法。ローズハート先生が解説してくれて、もっと好きになった魔法。
「せんせえ、どうしたらいなくならんといてくれる? せんせえがいないと、オレ——」
「ボクがいなくなってもキミは大丈夫なんだ。だからどうか落ち着いて、六秒数えて深呼吸をして——」
ローズハート先生の頭を浮遊した体温計がかすめました。幼子が駄々をこねるのと同じ速度と強さで。
「そんなわけないやん! せんせえの嘘つき! こんなみじめなアカンタレよりも、ほんとうの子の方が大事やって言えや!」
先生はぐっと喉を詰まらせました。全ての子供に与えられて欲しいものを、自分が与えられたかったものを、与えたいと思う気持ちは。親としてであれ、”先生”としてであれ変わりはなく。どちらかが嘘でどちらかが本当だとか、どちらかが優れていてどちらかが劣っているだとか、そんなことはないと強く確信しているのに。それを目の前の子に届ける方法が少しもわからなかったのです。
今や保健室の中を大小様々なものが飛び回っていて、最早双方の安全のために躊躇してはいられませんでした。ローズハート先生はマジカルペンを構えて、そして低い静かな声で。
「『首をはねよ』」
それぞれ耳障りな音を立てて、浮き上がっていた物たちが落ちていきます。少年は呆然と首輪に触れ、先生を見上げました。首輪が解かれても、ずっと泣きじゃくりながら座り込んでいました。やがてよろよろと立ち上がると、保健室を出ていきます。
「アヴァドン——」
「先生なんか、もう、知らんわ……」
その背中をローズハート先生が廊下に追ってしばらく見つめていたことを、振り返らなかった少年は知りませんでした。