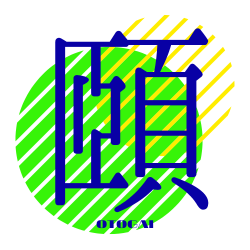「あ! 先生! ローズハート先生! お久しぶりです!」
「やあ、卒業以来だね。元気にしていた?」
「おかげさまで!」
メインストリートでカエルの獣人属の筋骨隆々な卒業生に声をかけられて、リドルは振り向いた。今日はハロウィーンウィーク、外部からの客に開かれた日だ。その中には卒業生や教員の家族も多く含まれる。リドルも末の子の手を引いて、校医としての仕事の合間に展示を回っていた。明日はトレイと上の子達二人が、休日を利用して回る予定だ。カエル獣人の彼も子供連れで、何人ものおたまじゃくしが迷子防止に尻尾を掴んで列をなしている。
「これは……全てキミの子かい?」
「ええ、まあ、そうです。縁がありまして養子を迎えましてん」
「……そう。愛らしいね。でも大変じゃないのかい? ……この数は」
彼はまだ二十代前半で、親子というよりは引率をするシッターのように見えた。子供というのは一人であっても目を離さずにいるのは大変だ。まして片手では足りない数の、好奇心旺盛そうな年頃の子たちともなればひとしおだろう。
「確かに大変ですけど、かわいくてしゃーないですわ!」
けれどにんまり笑った顔に曇りはなく、いい決断をしたのだろうと思われた。
そういえばこの、特徴的な訛の彼は、一年生の間保健室登校をしていた彼の、同郷で同寮で同学年だった。ああいった”難しい”生徒には何度も会ったが、彼は——アヴァドンは一際感情の起伏が激しかったので、よく覚えている。保健室登校をしていた頃、同郷として仲良くしてみてはどうかとそれとなくすすめたこともある。その時は全く伝わらなかったが、リドルが産休から復帰した後に一緒に行動している様子を見ることができた。
「そういえば……キミはアヴァドンと親しかったよね。まだ交流はあるのかい?」
「あー、親しいっちゅうか……。アイツが作った会社で働いてたこともありますよ。うちのコらと会うたのも、アイツのおかげやし。でも会社潰してからは、全然連絡取ってへんな……」
「そう、会社を……。キミたちが卒業して八年ほどなのに、大変な経験をしたんだね」
「いやほんっっっっっっまに色々ありましたわ!」
しばらく卒業後の苦労や在学中の思い出を立ち話すると、彼はおたまじゃくしたちを連れて去っていった。コロシアムのサバナクローの展示を見に行くらしい。
「さて、ボクたちは一通り見たし、そろそろ救護テントに帰ろうか…………っ!?」
繋いだ手の先にいたはずの末の子がいなくなっていて、リドルの顔からさあっと血の気が引く。立ち話している時、おたまじゃくしたちと遊びたがっていて、いっとき手を離すのを許した。尻尾の列車の中に加わって楽しそうに遊んでいた。けれどまさか、ついて行ってしまったとでも言うのか。
大慌てでカエルとおたまじゃくしたちに追いつく。けれどそこに末の子はいなかった。彼らも、ついてきていないと悲しげに首を横に振った。
「これだから……一瞬たりとも子供から目を離してはいけないのに!!!!!」
すれ違う生徒たち一人ひとりに探してほしいと半ば脅すように声をかける。カエル獣人の
彼も探してくれると約束してくれた。けれど気が休まらず、リドルは足早に学園中を歩き回った。すると、購買部のところで外部客の二人連れに声をかけられる。
「悪いが、今それどころではないんだ!」反射的にそう返してしまうが、女性二人はリドルを離してはくれなかった。
「——、——?」
「……え? なんですって?」
クモとワシの獣人属の女性たちは、ほとんど動物言語に近い古語を話した。リドルもかろうじてニュアンスがわかる程度で、話すことはできない。どうやら彼女たちもはぐれた連れを探しているようだった。
「はぐれたのなら、運営本部に行って放送を依頼してください。運営本部は校門の脇、体育館の前です」
地図を指で指しながらそう伝えるが、女性たちはしきりに校舎の中を指す。理解していないのかと、リドルは何度か同じ身振り手振りを繰り返したが、やがて思い至った。
「ああ、保健室を運営本部にしていたのは数年前のことですよ。今はこちらです」
聞き取る分には共通語を理解していたのだろう。女性たちはあっさりと納得して、リドルを解放した。
「……保健室か」
普段は保健室でお仕事をしているよ、と末の子に話したこともあったかもしれない。四歳児の判断で、そちらに向かったのかもしれない。リドルは魔法で箒を取り出すと、客たちの上を飛び越えて校舎へと向かった。
保健室の前に座り込んでいたのは末の子だけではなかった。
ボロ布のようなファッションの小柄な男が、うとうとしている末っ子にもたれられながら胡座をかいていた。先ほどの女性たちが見せた写真と同じ、クマの濃い髭面。その時はあまりの変わりようにわからなかったが、保健室の前で寂しげな表情をしているのを見ると、まるで在学中と同じように見えた。
「アヴァドン? アヴァドンじゃないか! 久しぶりだね」
「……ローズハート先生。お久しぶりです」
「運営本部が保健室前だったのはキミ達の在学中だけだよ。迷子を連れてきてくれたのかい?」
「この子……先生の子やろ。……あん時の?」
「いいや。その下の子だよ」
末っ子を抱き上げると、アヴァドンは微かに笑って立ち上がった。あの頃に比べればずっと平坦な笑顔は、彼が彼なりに時を重ねて二十代になったのだと告げていた。
「……元気にしておいでかい? 先ほどキミの同期にも会ったよ。会社を興したのだってね」
「潰してもうたし、あんま元気でもないなあ」
「……今は何を?」
「地元の団体の世話になりながら手伝っとる。コミュニティセンターとか、図書館作ったり……これ、一応、名刺」
取り出した折れ曲がった名刺には、NPO団体と『ルイン・アヴァドン』の名があった。
「……いい名前だね」
「弟とな、お互いに考えてん」
今の彼は一人ではないのだろう。あまり元気ではないとは言うものの、それでも誰かと一緒に生きていてくれることが、校医としてのリドルには心の底から嬉しかった。
数秒、互いに言葉が見つからないでいると、「もう行くわ」とアヴァドンは気まずそうに背を向けた。
「キミのことを探している人が運営本部にいるよ。……クモと、鳥の」
「ああ、あいつらか……」
「早く行っておあげ。……ルイン・アヴァドン」
青年が振り返る。夕陽の指す廊下で。
「また、いつでもおいで」
彼は否定も肯定もせず、無言で歩いて去っていった。
***
「欲しかったもんがもらえんかった時、もう絶対もらえん時、ずうっとその事ばっか考えんとあかんのかなあ」
突然の少年の問いに、トレイは口腔内のX線写真を指しながら答えた。
「歯並びの話か? 今からでも矯正はできるが……これは保険適用外だし大変だぞ」
「それもあるけど……なんかオレの十八年ってぜ~んぶそうやんか」
若く深刻な悩みに、トレイは写真を指す手を下ろして向き直る。じっくりと考えてから、真っ直ぐに少年の目を見た。
「君がそうしていたいなら、抱え続けていてもいいんじゃないか。でも、もしそうしていたくないなら、大変でも、変えることはできるよ」
「……つらくなくなるように?」
「それこそ、三年間歯医者に通ったのだってそうだ。もう君は虫歯に苦しまなくていい」
「結局歯の話かい!」
少し気分が軽くなって、「いきなり変なこと言うてごめんな、クローバー先生」と少年は笑った。
「いいんだ、別に。君のかかりつけの歯医者としての仕事のうちだよ」
あの時よりも少しだけ大人になっている少年は、その鷹揚な笑みを見て気がつく。
「……そうや、“先生”っちゅうんは、仕事や」
ローズハート先生も。クローバー先生も。仕事だから、こんなどうしようもなく無茶苦茶な子供にも優しく接していてくれていただけなのだ。
「勘違いして思い上がって……みじめやなあ……」
その肩をトレイは叩いて、キャンディを二粒握らせると、こう言った。
「仕事との向き合い方や感じ方は人それぞれだけどな……。でも、仕事しながら何も感じてないわけじゃないさ」
不安定な瞳でこちらを見上げる少年を、トレイは見つめ返す。
「先生の仕事は“みること”と……“みられる”ことなんだ」
芥子色の瞳を細めて、心からの言葉をかける。
「君が俺たちの働きを見て、できる限り健康に生きていってくれたら俺は……きっとリドルも。嬉しいんだよ。いい仕事したなって思いたいからな」
しんみりとした沈黙を打ち消すように、「歯と口腔は特に、な。実習先でもクリニックを見つけるんだぞ」と付け加えると、少年は「やっぱり歯やんけ!」と破顔した。
けれどその笑みは。いつもの空虚でやけっぱちな笑みよりも、どこか誇らしい感じがした。