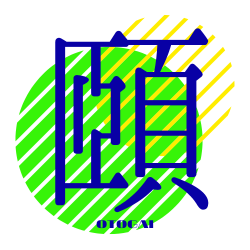【2】
「こんなところに放送室があるなんて知らなかったな」
職員室前の廊下を抜けると、奥まったところに扉がある。セカンドはそのドアノブに鍵を挿した。この時代のものではないはずのそれは錆が擦れる音を立てながらもすんなりと回った。
「今おそらく放送部は廃部になっている時期だと思います。記録を見る限り、廃部と創設を繰り返しているので……」
放送室はガランとしていた。カメラなどの機材があったらしいところには薄く埃が積もっていて、それ以外のところにはより濃く埃が積もっていた。隅のラックにはかつて大会に参加した時のものであろうテープや盾が納められていたが、刻まれた年はまばらだ。
「そうか、あなたたちはヴィル・シェーンハイトと同じ世代だから……おそらく彼が映画研究会を創設した際に放送部と機材を吸収したのでしょう」
放送室の中には更に防音性の高い小部屋があり、マイクと大小様々なつまみやボタンがついたコンソールから一目で放送するための部屋だとわかった。
「これもお前の代と同じか? 洗濯機はほぼ変わってなかったんだよな?」
「いや……これはかなり古いですね……」
よく見ればわずかに埃が払われているところがあって、教員たちが使用する際に最低限操作する部分なのだろう。トレイは総合文化祭での学園長のアナウンスを思い出していた。セカンドはその状態のコンソールに触れるのに抵抗があったようで、部屋の隅に放置されていたワイパーを持ち出すと几帳面な手付きで埃を払った。
「使えそうか?」
「……何とか。やってみます」
意図せず音を立ててしまわないよう、トレイは一度小部屋の外に出た。大きなガラス窓からセカンドの様子を見張る。セカンドは元々背筋を伸ばして椅子に座っていたが、更に姿勢よく座り直す。それからこちらに手を上げて合図をすると、放送中の赤いランプを灯した。
『食堂からのお知らせです。本日は土曜日ですが、食材の処理のため、特別ランチをご用意しております。数食限定ですので、ご希望の方はお早めにお越しください』
「君の世代では、よくこういうアナウンスをするのか?」
ランプが切れたのを確認してからトレイは小部屋のドアを開いた。
「食堂やミステリーショップからの依頼を受けてアナウンスすることはよくありますよ。特に食堂は食材のロスを無くしたいみたいで。昔は希望する生徒に格安で売ってたみたいですが……」
「それは俺にも少し心当たりがあるな……。妹さんは、本当にこれで誘い出されてくれそうか?」
「多分間違いないです。食べることと遊ぶことしか考えてない子ですが、その分食については真剣なので。NRCの食堂のメニューには元々強い興味を示していましたし、三十年以上前のメニューともなれば、絶対に来るはずです」
トレイはざるを棒で立てかけてその下にタルトを置くような形の罠を想像した。もしも彼の妹が食堂に駆けつけたなら、ざる……もといケイトが捕まえてくれる手筈になっている。その想像はリドルの娘としてはいささか緊張感に欠ける気がしたが、のびのびと食に対する興味を育むことができているのなら、きっとその子は幸せなのだろうと思った。だが、トレイが幸福かどうか気になってやまないのは。
「……なあ、リドルは——君のお父さんは、幸せか?」
たとえリドルのパートナーが自分ではないとしても、幸せならそれでいい。それだけを確認したかった。きっと幸せだろう。三人もの子供に恵まれて、その子どもたちは、少なくとも目の前にいる子は聡明ですこやかそうに見える。けれど返ってきた答えはトレイの予想とは違っていた。
「……わかりません。何が幸せなのかは人それぞれだから、親子であっても勝手に代弁したりしてはいけないと思うんです。でも僕から見て…………いや…………姉が失踪してしまってから……僕らがいなかったらしなくてもいい苦労をしてるんじゃないかってことばかり考えてしまいます」
”時の願い”とやらでどんな願いも叶うのなら、リドルが子を得ない未来にすることもできるのだろうか? だがそれは、目の前の少年を消し去るということだ。それに、セカンドだけの証言から、リドルが幸せではないと断言することはトレイにはできなかった。
「俺の知ってるリドルは、誰のことも見捨てないんだ。きっとそんな後悔はしていないよ」
そしてリドルと同じように他者のことを慮るセカンドの姿勢を、きっとリドルは誇らしく思うだろうと、トレイは思った。
「やっぱりきっと君の父さんのリドルは幸せなんだろうな。……リドルのこと、幸せにしてくれてありがとう」
「……そうなんでしょうか」
トレイのその言葉は、セカンドを慰めるための口先だけのごまかしではなかった。心からの感謝を込めて、セカンドに眼差しを向ける。
「おっと、リドルのパートナーにも、ありがとうって言わないとな」
なぜだろう、しかしそれだけは嘘のような気がした。リドルのパートナーの、トレイではない誰か。そこに遠くから感謝を投げるだけでいいのだろうか。
「……えっ?」
「俺達も早くここを離れないと。勝手に放送室を使ったのが先生たちに見つかると厄介だ」
「……そうですね」
もやもやとした疑問を振り払うように放送室を後にする。ちょうどケイトから、「ヤバい」「早く来て」というメッセージが届いていた。食堂までの廊下を、走らず早足で抜けていく。
***
食堂は特別メニュー目当ての生徒たちや自習に利用する生徒たちで混雑していた。ゴーストたちがあわあわと飛び回って、「誤報〜!」「特別メニューなんてないよ〜!」と言いながらもせっせと何かを作っている。シェフとしての矜持だろうか。
「迷惑かけちゃって申し訳ないな……」とセカンドが呟いたので、「俺が後で謝っておくよ」とトレイは答える。弟妹や後輩をフォローするのと同じ感覚で。セカンドがあまりにリドルに似ているものだから、トレイはリドルに対する感情を“弟みたい”と処理していた時のことを思い出していた。勿論“弟みたい”と“弟そのもの”は全く異なるし、リドルは“弟みたい”な他の存在全てと、勿論セカンドとも違っている。
「あー! いた!」とケイトが駆け寄ってくると、トレイとセカンドを厨房へと急かした。
「本当にヤバいんだって! 鈍感なトレイくんでも絶対わかるはず!」
「それって……どういう意味だ?」
「トレイ!」
厨房にはリドルと、一人の少女がいた。少女はてんやわんやと調理するシェフゴースト達を追い回すように厨房中を走り回っていて、リドルはトレイが入ってきたのに気づくと立ち塞がるようにその子を捕まえる。
「リドル! リドルがその子を見ててくれたのか?」
「厩舎で出会ってね。……クイズ、あれがキミのお兄さんで合っているかい?」
「え? あっ、お兄ちゃん!」
仮にクイズと呼ばれている少女はまだ大鍋のミネストローネが気になるようだったが、セカンドの方を向くと頷いた。
「怪我はない!? 合流できて本当によかった……」
セカンドは深いため息をつきながら、クイズを抱き締める。安堵で力が抜けてしまったのか、ほとんど妹に寄りかかるようになっていた。それをクイズは「お兄ちゃんは心配症だよねえ」と受け止めている。
「事情はケイトから聞いているよ。クイズはあまり説明が上手ではないからね。まさか……ンンッ、ボクたちの、こ、子供がこんなことになるなんて……」
「……えっ?」
赤面して、らしくなく言葉を詰まらせるリドルにトレイは戸惑う。
「……誰と、誰の子供だって?」
「だから、ボクたちのだよ。ボクと……キミの」
「…………………………えっ」
「うわっトレイくんの眼鏡がずれすぎて落ちた! こんなことあるんだ」
クイズが「パパ、はい」と落ちた眼鏡を拾い上げる。からし色の瞳は、女の子だからだろうか、トレイには母や妹を連想させた。だが髪の色はリドルと同じワインレッドで、つむじからは特徴的な癖毛が伸びていた。トレイの瞳にリドルの髪。だからといって。ツイステッドワンダーランドでは変身薬と魔法手術による同性間の生殖は一般化している。だからといって……。
「Qちゃん、きりっとして!」
「きりっ」
「ほら、この子の目元トレイくんにソックリじゃん!」
混乱してうわ言を呟くトレイの前に、ケイトがクイズの顔を突きつける。自分の顔立ちのこととなると、なおのこと実感がわかなかった。セカンドの方を見る。リドルにそっくりで、でも絶対にリドルではない存在。そのリドルではない部分が己由来かもしれないと思うと、レシピの肝心な部分を間違えてしまったかもしれない時のような、そんな覚束ない気持ちになった。
「トレイは、ボクとの間に子供がいる未来が、そんなに受け入れがたいのかい」
「違う! そんなこと……そんなことは絶対にないんだ。信じてくれ。でもなんだか……言葉にできない」
「あの子——ボクは仮にクイズ、と呼んでいるのだけれど——あの子は真剣な時の顔と笑った時の顔が本当にキミに似ているんだ。ボクがすごく好きなキミの顔なんだよ……」
「リドル……お前は……いや……俺は……」
浮ついた雰囲気だったキッチンは一転して沈鬱と混乱に満ちてしまった。「今そういうすれ違いやってる場合じゃないじゃん、も〜っ……」とケイトが深くため息をついた。
その数秒後。
「迷子の迷子の小鼠ちゃんたち、さあ、大いなる過去を知ろう、知らしめようか!」
「ドミノさん! ちょっ……何やってるンすか!」
突如として、皿一つ分の隙間を開けて封鎖されていた厨房のドアが蹴り開けられ、女が大股で踏み込んできた。その後ろにはエース、デュース、監督生とグリムもいる。
「お姉ちゃん!」
「こんなに早く見つかるなんて……!」
「馬鹿だね、私は君たちのお姉ちゃんだよ? 考えてることなんてお見通しさ」
女はその場にいる面子を見渡した。
「そっか、正体を明かして父さんたちを頼ったんだね。しょうがないか。じゃあ私も変装魔法を解いても良さそうだ」
髪を後ろへとかきあげる。特徴的な癖毛だけが残る。我の強さに反してどこかぼやけた印象だったのが、靄が晴れるように明らかになっていく。着いてきた四人全員が、なぜ気が付かなかったのだろうと目をこすった。
「緑の髪に灰色の目に……あのテッペンの髪……!」
「くそっ、もう足して二で割ってんなあ……としか思えない……! キケンでキレイなお姉さんに対するときめき返してくれよ!」
リドルとトレイとケイトはもやつきを振り払うようにしてマジカルペンを構えると、セカンドとクイズを庇うように立ちはだかった。
「エース、デュース、監督生にグリム。詳しい状況を説明している暇はないよ。とにかくこの子を捕らえるんだ」
「言われなくても……危険人物を見張るつもりでここまで来たんで!」
「頼もしいな……さて、お前は追い詰めたつもりでも、俺には誘い込まれて囲まれたように見えるぞ。大人しくした方がいいんじゃないか?」
ドミノの背後ではエースとデュースがマジカルペンを構えている。「私が? 大人しく? するわけがない。おっと、この時代のパパはまだ知らないか、私を……」
毛を逆立てたグリムの後ろで監督生が、道理でヤバい人なわけだ、と呟いてデュースに「お前は隅に……あの女の子と一緒にいろ!」と身を案じられた。あるいは、SHOWDOWN……と呟いてエースに「お前シリアスな時に限ってそれ言うけど、マジ何なの?」と呆れられていた。